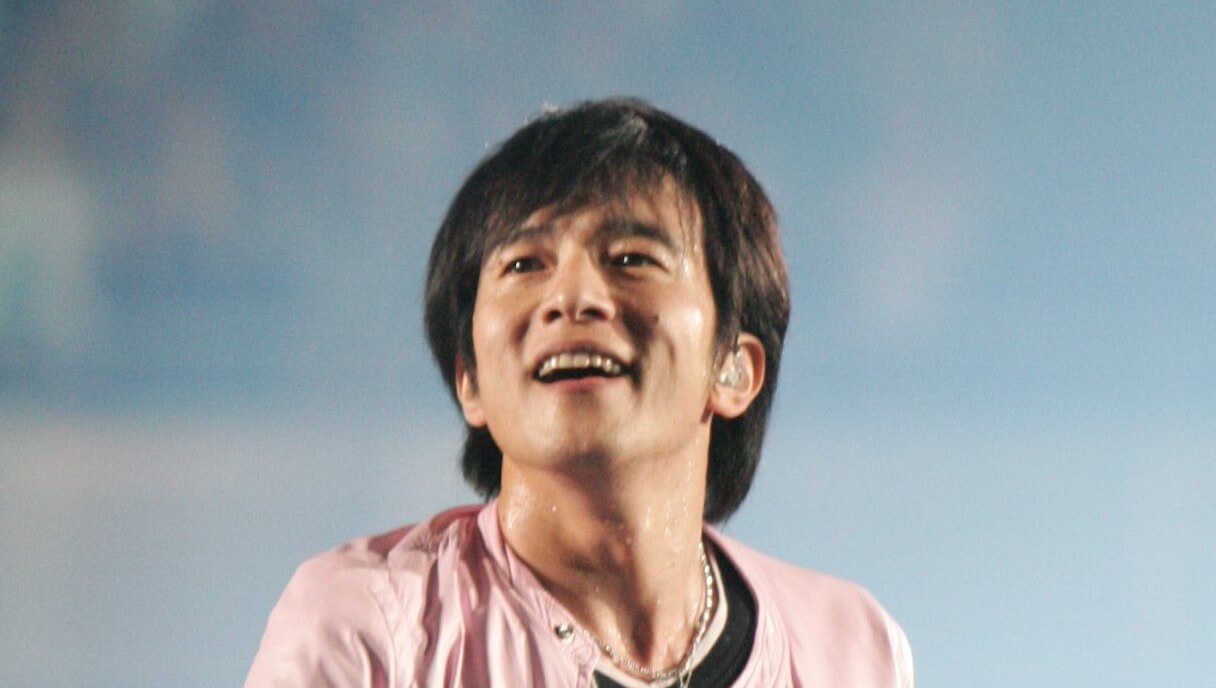Mr.Children『Q』とその後――“深海”から帰還した彼らの「優しい歌」
#Mr.Children #TOMC

本連載では、ここ3回にわたって、1994年以降のMr.Children作品をサウンドやアレンジ面、制作プロセス等の観点から語ってきた。「Mr.Children編」最終回となる本稿では、彼らがいよいよ真の意味で“深海からの脱出”を果たすことになる『Q』を中心に、現在の活動に至るまでの流れについて記していきたい。
<第1回はコチラ>
<第2回はコチラ>桜井和寿の才能が惜しみなく注ぎ込まれた『Q』
第3回で記した通り、『DISCOVERY』(‘99)前後は、桜井の自宅環境へのPro Tools導入~バンド4人だけでのセッション敢行など、プロデューサー小林武史との共同作業だけでない制作のあり方を掴み始めた時期に当たる。これを経ての『Q』(‘00)では、そうした自由な制作姿勢がバンド史上最も加速していくことになる。
この時期の桜井について、小林は「プロデューサーへの反抗期」「僕のアドバイスなど全く聴かなかった」と述べつつ「あの頃の桜井は最高にカッコよかった」「まるでかつてのジェームズ・ディーンのようでもあった」と振り返っている。一方の桜井は「ずっとプロデュースを受けてきて、意味合いのようなものを常に考えて作っていたことへの反動で、無意味・無秩序への魅力を感じていた」と語っており、ある意味ではMr.Children史上、最も桜井自身の意思・自我・こだわり・エゴが自他のブレーキなしに注ぎ込まれた作品のひとつが『Q』なのかもしれない。また、彼らはこの15年後、『REFLECTION』(‘15)の一部収録曲から、小林の手を離れてセルフプロデュースを始動させていくが、『Q』はそうした後年の歩みを紐解く上でも重要なアルバムだろう。
『Q』はリリースに向けた締め切りが存在しなかったと言われており、アルバムコンセプトも、桜井曰く「とにかく何も決めていなかった」という。したがって各楽曲の制作時期・曲調にはかなりバラつきがあるが、今回は「冒険的なアレンジで聴かせる楽曲」「自然体のソングライティングが光る楽曲」の二軸で主に振り返っていきたい。まずは前者について触れていこう。
“実りある無駄”から生まれた冒険的アレンジ
先ほどの桜井の「無意味・無秩序への魅力」という言葉に通ずるが、ドラマーの鈴木は『Q』の制作時期を振り返り、「バンドが“実りある無駄”へと向かっていた」と表現している。これを象徴するのが、有名な「曲のテンポ(BPM)をダーツで決めた」というエピソードだろう。得点を加算していくカウントアップというルールでダーツをプレイし、複数回投げた合計の点数をBPMにする。そしてこのBPMに合わせて、まず鈴木がドラムを叩き、そのパターンをループさせ、今度は他のメンバーがこれに合わせて即興で思いついたフレーズを何時間も弾く――こうした一般的なポップスの制作現場とはかけ離れた雰囲気の中で大まかな構成を決め、そこから桜井が歌詞のないメロディを歌い出し、曲の輪郭を少しずつ形作っていく。こうして生み出されたのが、二転三転するプログレッシブな展開と突き抜けた“明るさ”を持ち合わせた楽曲たちだ。
中盤で急加速しながら高らかに自己を肯定する「CENTER OF UNIVERSE」。エフェクト・エディットを交えた重いグルーヴと、性的なメタファーを交えた軽快な言葉遣いが同居する「その向こうへ行こう」。別の演奏を切り貼りしたかのように突飛なリズムチェンジを見せるが、マーチを基調としているためアングラ感はいささか希薄な「Everything is made from a dream」。どの曲も楽曲構造上、『深海』『BOLERO』を凌駕するアグレッシブさを持ちつつも、いずれも暗いムードに沈むことなく、最終的には肯定的なメッセージをもって締めくくられている。音楽市場を席巻した“ミスチル現象”期の作風を鮮やかに塗り替え、ネクストレベルに到達したと言っても過言ではないだろう。
なお、この方向性で特にコアファンから熱い支持を集める「友とコーヒーと嘘と胃袋」については、本稿の後半で詳しく触れる。続いて「自然体の楽曲」について、なぜそれらが生み出されたのかについても掘り下げながら向き合っていこう。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事