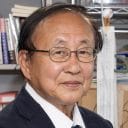推古天皇“中継ぎ説”を覆したのは新史料ではなかった 歴史学に染み付いたジェンダーバイアスという罠
#歴史 #ジェンダー
昨秋、国立歴史民俗博物館で開催された「性差の日本史」展が大きな反響を呼んだ。ジェンダーという観点から、歴史の新たな側面を照らす展示となった。歴史学という学問の世界そのものもジェンダーバイアスと無縁ではない――。(「月刊サイゾー」2021年9月号より転載)

「歴史は勝者によって書かれる」──作家ジョージ・オーウェルが述べた、よく知られた箴言だ。「歴史は強者によって書かれる」と言い換えることもできるだろう。時代時代で権力を握り、政治や経済、社会を動かした人物たちを中心に語られるもの。それが大文字の歴史だ。
日本で歴史が語られるとき、表舞台に立つのは大半が男性である。日本史の教科書に載っていた肖像画や写真を思い出せば、ほとんどが男性だったはずだ。女性やセクシャル・マイノリティなど、社会の権力構造における弱者の視点から歴史が語られることは少ない。
昨秋、千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館で「性差(ジェンダー)の日本史」と題した展示が行われた。古代社会で「男」と「女」の区分はいつどのようにして生まれたのか、中世の女性の働き方や政治との関わり方、近世・江戸時代の大奥の政治的権能、遊郭を中心とした売買春の実情、そして近代化と女性の生き方との関係など内容は多岐にわたり、280点以上の資料を通じて紹介する大掛かりなものだった。同展示は話題を呼び、コロナ禍に加えて不便な立地をものともせず大勢の入場者が訪れ、図録は7000部を売り上げた(2020年12月時点)。博物館のプレスリリースには以下の記述がある。
「時の流れに浮かんでは消える無数の事実を指す『歴』と、それを文字で記した『史』。日本列島社会の長い歴史のなかで、『歴』として存在しながら『史』に記録されることの少なかった女性たちの姿を掘り起こす女性史研究を経て、新たに生まれてきたのが、『なぜ、男女で区分するようになったのか?』『男女の区分のなかで人びとはどう生きてきたのか?』という問いでした」
ここに登場する女性史研究とは、歴史の中の女性に光を当て、女性が社会でどのように位置づけられていたかを研究する歴史学の分野のひとつ。日本では戦前に端を発し、戦後1970年代には在野の女性研究者を中心に裾野を広げていった。80年代に入って『日本女性史』(東京大学出版会)全5巻の大著が刊行され、総合女性史研究会(現・総合女性史学会)が創設されるなど大きく広がりを見せた。そして90年代以降、ジェンダー概念を取り込んでジェンダー史研究も盛んになっていった、という経緯を持つ。
女帝“中継ぎ”説を覆す 思い込みを排した研究
冒頭で書いた通り、巷間語られる歴史は男性を中心としたものだ。それは歴史学という学問の世界でも同じだという。『歴史を読み替える ジェンダーから見た日本史』(編・久留島典子、長志珠絵、長野ひろ子/大月書店)の冒頭では、以下のように書かれている。
「歴史学は、けっしてジェンダー中立な学問として成立したわけではない。近代科学としての歴史学は、法学や経済学と同様、19世紀ヨーロッパで確立した。当時、学問は男性の領域とみなされ、歴史学の研究対象もまた、国内政治や国際関係、経済活動などのいわゆる『公的領域』に限られていた」(同書P2)
「(引用者注:日本における)従来の歴史学では、女性たちの居場所は私領域であることが自明とされ、公的・政治的領域に存在するのは、例外的・偶然的として片づけられるか、時には不在とみなされてきた」(同書P12)
学問や研究という行為もまた、ジェンダーバイアスと無縁ではいられないというわけだ。それを端的に指し示すのが、古代日本史研究における女性天皇(女帝)に関する学説の変遷だ。歴史の授業で、こんな説明を聞いたことはないだろうか。
「飛鳥時代、聖徳太子が仕えた推古天皇は女性だが、朝廷の権力争いが激化した結果即位するにふさわしい年頃の男子がいなかったために、“中継ぎ”として天皇になった」
この通説を信じている人は現在でも少なくないはずだ。だが、歴史学の世界では近年この説は主流ではなくなっている。
“女性天皇(女帝)中継ぎ説”が生まれた背景には、明治政府の取り決めが関わっていた。
「十九世紀末に大日本帝国憲法と旧皇室典範が制定され、法的に女帝・女系即位の可能性が報じられた過程で(中略)明治政府は、歴史上の女帝即位は幼帝に皇位を継承させるための『権宜(仮の措置)』だったと結論した。この考えは、その後の歴史学会でも影響を保ち続けた」(『ジェンダー分析で学ぶ 女性史入門』編・総合女性史学会/岩波書店)
その後、古代の女帝をめぐる研究はこの視点によってなされ、長らく主流を占めた。天皇の座につくのは男性が基本であり、女性はあくまで例外――この説の呪縛から逃れる動きは、90年代末になってようやく起こったという。現在、この分野の第一人者として活躍する歴史学者・義江明子氏は2018年、それまでの研究成果をまとめた『日本古代女帝論』(塙書房)で角川源義賞を受賞した。一般向けに出版された『女帝の古代王権史』(ちくま新書)のあとがきで同氏はこうつづっている。
「(引用者注:同書を執筆するにあたって)基本姿勢としたのは、史料批判の徹底である。『日本書紀』はもちろん『続日本紀』についても、近代以降の価値観/思い込みによる解釈を排し、古代の史書編纂時の政治的意図や理念をも考慮しながら、一つ一つの文言を吟味していった。その結果、かつての通説的な『中つぎ』女帝とは大きく異なる古代女帝像を提示することになった」
思い込みを排して史料(資料)を丹念にあたるのは、外野からすれば「学術研究の基本なのでは?」と思わされるところである。それだけに、ごく当然のものとして歴史学の世界にジェンダーバイアスが根付いていたことをうかがわせる。前掲の『女性史入門』ではより明確に、その点に言及している。
「(引用者注:女帝研究の進展は)新しい史資料が出てきた結果ではない。近代天皇制成立の過程で作り上げられた『天皇は男性がなるもの』との無意識の領域まで浸透していたジェンダー・バイアス(男女の役割に関する固定観念)をはねのけ、史資料を虚心坦懐に読み解き分析した成果である。男性が生物学的本質的に支配者に適していたゆえではなく、歴史的に構築されたことが解明されたのである」
歴史好きをくすぐる“新事実”の宝庫に
女性天皇の歴史をめぐる研究は、皇室をめぐる女性・女系天皇容認の議論とも関わってくる。歴史的発見が現代にも影響を与えうる、わかりやすくセンセーショナルなトピックだろう。逆に言えば、直接的に現代と関わるほどの重要なテーマに関してすら研究が始まってわずか20年余という状況なのだ。「性差の日本史」展でも展示された通り、中世や近世の政治空間における女性の権能もこれから明らかになっていくことは多いと考えられる。
そうした歴史の読み替えは、まだまだ一般に知られていない。本稿で引用した『ジェンダーから見た日本史』はそうした観点から「歴史教育にジェンダー主流化」を目指して刊行されている(『世界史』版も存在する)。
「これまで知られてこなかった、衝撃の真実!」などとうたわれた歴史本は人気がある。近年は一般にあまり注目されてこなかった室町時代が脚光を浴びるなど、ある種ニッチな歴史の“真実”は人々の興味を惹きやすい。ジェンダーの観点から見た“新事実”は今後もどんどん掘り起こされていくはずだ。歴史好きを自認するのであれば、この視点を身につけておくと、より新しい発見を楽しむことができるのではないだろうか。
(文/五月 晶)
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事