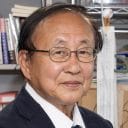【田澤健一郎/体育会系LGBTQ】童貞とバカにされながら野球に没頭した専門学校の部員
#体育会系LGBTQ
社会に広がったLGBTQという言葉。ただし、今も昔もスポーツ全般には“マッチョ”なイメージがつきまとい、その世界においてしばしば“男らしさ”が美徳とされてきた。では、“当事者”のアスリートたちは自らのセクシュアリティとどのように向き合っているのか――。(「月刊サイゾー」2021年9月号より転載)

「阪神、調子ええな」
「やっぱマートンと城島がデカいって」
放課後の私鉄沿線。電車の中で学校帰りの高校生たちがプロ野球の話題で盛り上がっている。丸刈りの精悍(せいかん)な体つき。校名が入ったそろいのバッグを持っている。一目で野球部とわかる集団だ。電車がベッドタウンの駅に着いた。その集団からひとり、髪の長い少年が電車を降りていく。
「がんばってな」
「おお、ありがとう」
「あの別れる瞬間が一番つらかったですね」
関西出身とは思えない、滑らかな標準語で話すのは飯島康士(仮名)。整体師として働きつつ、週末を中心に社会人野球の硬式クラブチームでプレーを続けている29歳の現役アスリートだ。
そう聞けば、10代の頃は高校球児……とくるのが相場だが、康士に高校野球の経験はない。
「家が貧しく、高校では野球どころか部活そのものができなかったんですよ」
中学で野球に打ち込んだ康士としては、当然、不本意だった。しかし、幼少期に父が病没。必死で育ててくれた母と祖父母のことを思うと、ワガママを通すことはできなかった。野球は大好きだったが、強豪校のスポーツ特待生になれるまでの実力もなかった。
「だから、電車の中で野球部気分を味わっていたんです」
康士が通っていた高校が位置するのは、大阪市内のど真ん中。校地が限られるため、野球部の練習グラウンドは校舎から電車で遠く離れた郊外にあった。野球部の生徒たちは、授業が終わると私鉄に乗って練習に向かう。帰宅部の康士も、彼らと同じ電車に乗った。家がちょうど同じ沿線にあったのだ。
「ただ、思い返してみると、『野球部と一緒にいたい』という私の気持ちには、高校野球に対する憧れだけではなく、彼らに対する恋愛感情にも似た気持ちも、少し混じっていたのかもしれません」
そう言えるのは、今は自身がゲイだと、ポジティブに認めることができているからだ。
「嫌われたくない」から自覚しても認めなかった
「今だから言えますけど、高校時代から『もしかして』と感じる瞬間はあったんです。でも、認めたくなかったというか……」
中学生になる頃から、友人たちと同様、年相応に女性への興味が高まった。ただ、それと同じ感覚で男の裸にも興味を引かれる自分がいる。
「アイツはどんな体をしているのかな、みたいな感じで、つい見たくなる。友達とスーパー銭湯に行くのとか、ちょっと楽しかった」
ただ、当時の康士は、LGBTQに対する知識が圧倒的に少なかった。というよりも、「陰キャ」的と自身が回想するように、10代の頃の康士は、気は優しいが、自分から前に出ていくような人間ではなく、性的にも奥手だった。
「彼女はできず、好きなコはいたけど……付き合いたいなんて積極的に動くこともなく、果たして本当に好きだったのか……」 女性に対して、いつまでも「かわいいな」以上に盛り上がらない自分。一方で男性への性的な興味はなくならない。
「もしかしてゲイなのかな……」
奥手の康士も、テレビなどを通してゲイのことは少しずつわかってきていた。
ハッキリと自覚したのは、高校卒業後、専門学校に通っていたときである。
「高校卒業前に受けた、ある公務員の試験に落ちちゃったんです。就職はそれしか考えていなかったから、どうするかとなったのですが、家族と相談して専門学校から公務員を目指すことになりました」
その学校に「脱ぎたがり」の先輩がいた。
「自分の体に自信があって、酔うとすぐ脱ぐんですよ(笑)。で、『触れよ!』となるまでが毎回のパターン。まぁ、男同士のふざけ合いですよね。でも、私は楽しかったんです。『何やってるんですか~』とか言いつつ、触って喜んでいる自分に気づいて、もう認めるしかないな、と」
しかし、カミングアウトはもちろん、積極的にゲイのパートナーを求めるようにはならなかった。
「ヘンな目で見られるかな、『アイツに近づかないようにしようぜ』とか言われたら嫌だな、という気持ちが強くて……」
端的に言えば怖かった。決して目立つタイプではなかった康士は、昔から「嫌われたくない」という気持ちが強かったという。
「だから、自覚したけど認めてない、みたいなモヤモヤ状態でしたね」
そして、ゲイであることを隠さねば、という気持ちを、さらに強くする転機が訪れる。
野球を再開したのだ。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事