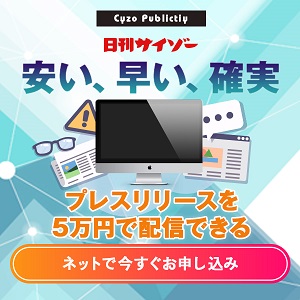『光る君へ』天才歌人かつ“都合のいい女”和泉式部(泉里香)と最上流階級・親王をめぐるスキャンダル
#光る君へ
『光る君へ』は後半へ――業深い恋のドラマ

また、ドラマの和泉式部ことあかねが「親王さま」とだけ言っていた男性ですが、史実でも当時、現在進行系で続いていた「帥宮(そちのみや)」こと敦道親王との熱愛を指しているのだと思われます。「熱愛」というと美しいですが、当時の上流社会を騒がせた「スキャンダル」でもありました。和泉式部自身が執筆したとされる『和泉式部日記』にも詳しく描かれています。
和泉式部の生まれ年は、天延2年(974年)から天元元年(978年)あたりではないかといわれています。ドラマのあかねも20代中盤から後半にさしかかったばかりでしょうか。まひろこと紫式部とは10歳ほど離れているはずです。
学者だった大江雅致の娘に生まれた彼女は、幼少から利発で、天才歌人でもあったようです。彼女はのちに和泉守をつとめた橘道貞の妻となりました。つまり、紫式部同様に中級貴族の出身だったのですね。和泉式部という女房名は、彼女の最初の夫にちなんだものだといわれているのですが、夫ある身でありながら、和泉式部は皇族――つまり最上流階級出身である為尊(ためたか)親王と恋仲になってしまいます。
そして彼が流行り病で亡くなると、悲嘆の彼女を慰問という体裁で口説きにやってきた親王の弟・敦道親王とも恋に落ち、夫と娘(後の小式部内侍・こしきぶのないし)を捨て、敦道親王と北の方が暮らす邸に「召人(めしうど)」――つまり女性使用人として入り込んだのでした。
当時の「召人」とは現在の「愛人」というような意味ですが、男性側には「まったく責任が発生しない」という点で「都合の良い女」でしかない存在です。今の時代以上に身分がハッキリしているのが平安時代の特色ですから、正規の結婚生活を捨て、生家の身分が違うので正規の結婚などありえない高貴な男性の召人になるという人生の選択肢は、あまり賢明ではあり得ません。しかし、それさえ厭わない史実の和泉式部は「恋愛至上主義者」であったわけですね。
ドラマのあかねこと和泉式部の恋のあれこれがどの程度、詳しく描かれるかは興味深いのですが、敦道親王との関係を描いた『和泉式部日記』によると、高貴な生まれで、親王の北の方(正妻)を、たかが召人の身分の和泉式部が圧倒し、やがて失意の北の方が親王邸から出ていってしまうという異例の展開となりました。
本来、北の方というものは、夫の抱える妻妾を管理・監督し、彼女たちと自分の夫との間にトラブルが発生すれば、それを仲介する役割さえ期待されていたので、本来ならば歯牙にもかけるべきではない和泉式部を、自分と対等の女性として考えてしまったのが敦道親王の北の方でした。こういう業深い恋のドラマが、少しでも映像化されるとグッと面白くなる気はするのですが……。
いずれにせよ、こうやって文学や当時の文化について話ができる「大河」というのも良いものですね。そろそろ後半にさしかかった『光る君へ』ですが、今後の展開に期待しましょう。
<過去記事はコチラ>
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事