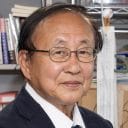Mr.Children『Q』とその後――“深海”から帰還した彼らの「優しい歌」
#Mr.Children #TOMC
Mr.Childrenが息を切らして駆け抜けた道

先述の通り、彼らは『Q』の翌年に2枚のベスト盤をリリースし、それまでのキャリアを一度総括する。まもなくデビュー10周年という分かりやすい節目であったのはもちろんのこと、音楽的な冒険と初期の作風への回帰が同居する『Q』が生まれたこと、そして付け加えれば、同作がセールス面で若干の苦戦を強いられたことを思えば、全てにおいて最適なタイミングでのリリースだったように思える。
ただし、当時の彼らの内情はもっと複雑なものだったようだ。桜井はベスト盤リリース時のインタビューで、『Q』のツアー中に「流れ的にここで解散するのが一番キレイだ」とまで思ったと吐露している。桜井自身の望みだったという「人間としての生活と音楽が密着し、みんなが楽しく、ギスギスしないで音楽をやりたい」という思いが結実した作品が『Q』であり、それゆえバンドとして向上心を見出せない状況に陥ってしまった――というのがその理由だという。そうしたMr.Children史上最大の危機的状況の中で制作が進められ、小林の「いろいろ考えてから出したほうがいいんじゃないか」という制止の声も振り切ってリリースされた楽曲こそ、本連載でも何度となく名を挙げてきた「優しい歌」である。
本曲の歌詞については多くのファンが、ときに桜井のプライベートも絡める形で様々な考察を試みている。この点は他に譲るとして、ここでは簡単に楽曲が生まれた背景についてまとめておきたい。
『Q』のツアーで桜井は、デビュー9年を迎えた自分たちのオーディエンスの幅広い年齢層を目の当たりにしたことで、「多くの人にとってのMr.Children像を一度、ひとつにまとめたい」「自分たちのやりたいことやエゴは置いておき、今までのMr.Childrenを好きでいてくれる人をとにかく一回肯定したい」と思ったという。これは先述したベスト盤の制作動機のひとつとなり、その準備を進める中で桜井は「凄くいい曲だ」と思える新曲ができた。興奮した桜井は鈴木にメールで本曲を共有し、鈴木は「デビューする頃にライブハウスでやっていた曲にも似ていて、逆にそれが新鮮だった」という感想を抱く。そして鈴木は桜井への返信の末尾を「僕らは生涯、現役でいましょう!」という言葉で締めくくった。Mr.Childrenの「これまで」と「これから」をつぶさに歌った本曲はしばしば“第二のデビュー曲”とも称されるが、本曲はメンバー自身にとっても瑞々しく、強く心を動かされるものだったに違いない。それも、解散が検討されていたような時期においてはなおさらのことで、「優しい歌」はMr.Childrenとして文字通り、起死回生の一曲となった。
そうしたなか、桜井は『Q』以降のMr.Childrenの音楽性について「僕らはロックか?ポップか?と思った時に『やっぱロックにはなれない』」「今までだってポップだったし、じゃあ巨大な“ポップの恐竜”でありたい、あり続けるべきなんじゃないか」と述べており、それゆえにベスト盤を引っさげた2001年のツアーのタイトルは『POPSAURUS』となった。この発言はそれこそ、本連載の第1回で紹介した『Atomic Heart』期の桜井の発言――U2の「変化することでより多くのものを巻き込んでいく姿勢」を見習って「バンドをもっと”大きな怪獣”にしたい」と語ったこと――と驚くほど綺麗にシンクロしている。そうして彼らの2000年代は『SUPERMARKET FANTASY』(‘08)を頂点とする、ポップバンドとしての新たな黄金期を迎えるに至った。
そして桜井の「巨大な“ポップの恐竜”であり続けたい」という発言の通り、「優しい歌」を境に、『深海』から『Q』までさまざまな形で追求されてきたバンドサウンドの主張はやや後退し、「Mr.Childrenの録音作品」としての完成度をいかに向上させるかが、彼らの大きな目標のひとつとなっていく。この2001年以降の歩みの詳細はまた別の機会に譲るが、重要なのは、『REFLECTION』(‘15) の一部楽曲以降、バンドが小林のプロデュースから離れていくこと、そしてそこから文字通り、4人のバンドサウンドが再び前面に出てくるところだろう。かつて彼ら自身で選んだ「Mr.Childrenというブランドをいかに育んでいくか」という道から、再び新たな一歩を踏み出した近年のアルバムは快作揃いだ。
『重力と呼吸』(‘18)ではMr.Children史上もっとも重厚とも称される立体的なサウンドが楽しめ、それこそ『深海』や『DISCOVERY』以来の「音像で驚かされる」作品に仕上がっている。そして最新作『SOUNDTRACKS』(‘20)では『Q』以来およそ20年ぶりの海外レコーディングを敢行。サム・スミスやU2との仕事で知られるスティーヴ・フィッツモーリスがプロデュース・編曲・レコーディングエンジニアとして参加し、近年のMr.Childrenサウンドが音の配置・抜き差しのレベルから大幅に再構築されたことで、世界標準のポップ・ミュージックへと更なる進化を果たしたアルバムとなった。『Q』までの苦悩・混沌と自由の時代から多くの年月を経て、改めてMr.Childrenがバンドサウンドに向き合い、様々な音楽的冒険から充実作を生み出し続けているさまは、彼らのキャリアの変遷を知る音楽ファンならばきっと誰もが心踊るはずだ。
Mr.Childrenは、幅広い嗜好を持つ無数のリスナーからの期待を背負い、多くのスタッフ・関係者の生活を支える立場にありながら、さまざまな音楽的ボキャブラリーやアイデアに満ちた、日本でトップクラスの音楽家集団である。本稿を含めたこれまでの全4回での説明の通り、Mr.Childrenは『Q』までのデビュー10年弱の間に非常に濃密なキャリアを過ごしてきたが、現在の彼らは『Q』の時期と並んで、創作面で自身の興味をどこまでも追求できる自由を掴んでいる印象がある。『SOUNDTRACKS』もキャリア最高傑作との呼び声が高かったなか、彼らの次回作はどれほどのものになるのか。鈴木の言葉の通り、きっと「生涯現役」であろう彼らの終わりなき旅を、いつまでも追い続けていきたい。
本連載「ALT View」は次回、日本だけでなく世界中にファンを持つ女性音楽家のニューアルバムについて、主にサウンドの観点にフォーカスしながら掘り下げていきたいと思う。
◆
本稿におけるMr.Childrenのレアな制作エピソードは小貫信昭氏の『Mr.Children 道標の歌』(水鈴社)を参考にさせていただいた。
本稿で紹介しきれない楽曲を含め、Mr.Childrenのオルタナティヴ・ロック方面の楽曲をまとめたプレイリストをSpotifyに作成したので、ぜひ新たなMr.Childrenの魅力の発見にご活用いただきたい。
B’z、DEEN、ZARDなど……本連載の過去記事はコチラからどうぞ
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事