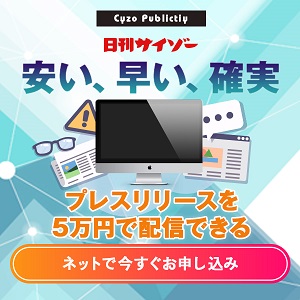父・後白河法皇に愛されなかった以仁王と、父・時政に愛された「江間四郎」北条義時
#鎌倉殿の13人 #大河ドラマ勝手に放送講義 #以仁王 #北条義時
北条家の“正規メンバー”ではなかった「江間さん」北条義時

話をドラマの本筋に戻しましょう。後白河法皇からの密書らしい怪文書が届き、それが頼朝が挙兵を決意する大義名分になったという描かれ方でしたが、一般的には「以仁王の令旨」を受けて頼朝が行動を起こしたとされています。
打倒平家のために諸国の源氏らに蜂起をうながしたこの「以仁王の令旨」ですが、実物が現存しておらず、『平家物語』などさまざまな軍記物=フィクションの中に不完全な形で引用されているばかりで、実際の内容についてはよくわかっていません。以仁王は、自分を「壬申の乱」で皇位を奪い取った天武天皇や、仏法の守護者である聖徳太子などになぞらえ、福原に幽閉された父・後白河法皇を救い出し、新たな天皇として自分が君臨すると宣言していたようですが……。
筆者は、アニメ『ドラえもん』のジャイアン役、あるいはチャラい若い男性の役で定評のある声優の木村昴さんが以仁王をどう演じるのか、興味津々でした。しかし、想像は良い意味で裏切られ、木村さんのセリフはワンシーンだけでしたが朗々と響き、格調高く聞こえましたし、立ち居振る舞いも立派でした。惜しむらくはあっという間に戦死となり、すべての登場シーンを合計しても数分程度で終わってしまったことでしょうか……。
ちなみに八条院は、以仁王の戦死後も京都と関東を行き来し、頼朝の挙兵計画を支えた人物たちを後援し続けたとされます。ドラマに登場した文覚(市川猿之助さん)も、頼朝の挙兵計画を支えた立役者の一人として歴史関係者には一般的に認識されています。もっともドラマでは、“謎の僧侶”どころか、出どころ不明の怪しいドクロを持ち歩いている薄汚い僧形の詐欺師みたいな存在として描かれていましたが……。今後の活躍に期待、といったところでしょうか。ナレーションで語られていたように、平家の栄華にも確実にほころびが生じ始めていました。
ところで、前回の放送では、八重(新垣結衣さん)が、北条家と川を挟んだところにある「江間館」に暮らしているというくだりも筆者の興味を引きました。
江間館の主は、八重の実家・伊東家に仕える家人という、八重とは身分違いの結婚をした江間次郎なのですが、鎌倉幕府の公式史『吾妻鏡』では、我々が「北条義時」として認識している人物も、実は“江間さん”として呼ばれることのほうが多かったのです。義時が「江間四郎(えまのしろう)」「江間小四郎(えまのこしろう)」「江間殿」などと呼ばれているケースが59例あるのに対し、北条の「苗字」で記されたケースはわずか23例に過ぎません(細川重男『執権 北条氏と鎌倉幕府』講談社学術文庫)。
史実の北条義時こと江間四郎は、北条時政の子供ではあるのですが、正妻とは呼べない女性との間に生まれた男子にすぎませんでした。つまり本家=北条家の“正規メンバー”というわけではなく、その庶家(≒分家)である江間家を継がせられていたのです。
ですから史実では、あの北条館の対岸にある江間館の主は義時だった……といえるかもしれません。まぁ、それだけの話で、「史実で八重と結婚したのは実は義時だった」とかそういう面白い話にはつながらないのですけども。
義時が“本家”こと北条家を継いでいくことになったのは、かなり運命に翻弄された結果にすぎないわけですが……このあたりも今から詳しく語りすぎるとドラマが面白くなくなるかもしれないので、筆者は口を閉じましょう。ただ、『吾妻鏡』が書かれた時代、つまり生前の義時は“北条氏というより江間氏の人”という認識が世間では強かった、ということは知っておいてもよいかもしれません。
しかし、「江間」というのは所領に由来する「名字」です。父宮である後白河からは所領も与えられず、顧みられることのなかった以仁王に比べ、ちゃんと所領を与えられていた義時は、父・時政からそれなり以上に愛されていたことがうかがえるのは面白いところです。
<過去記事はコチラ>
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事