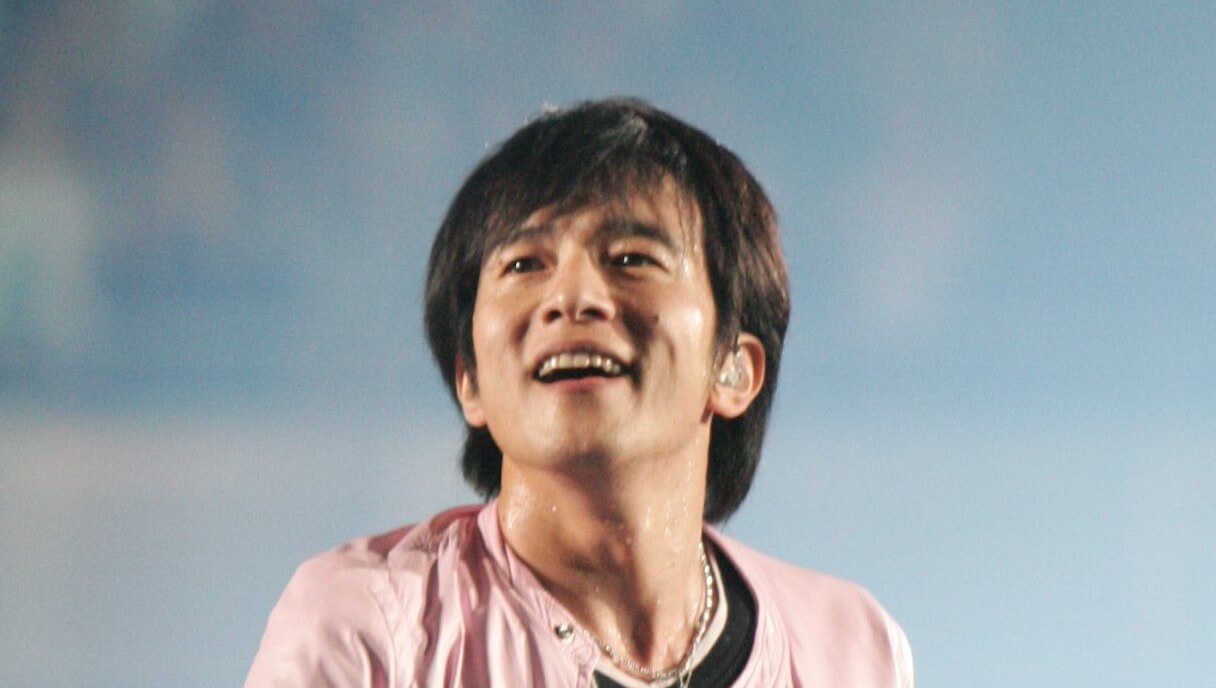Mr.Children『深海』はなぜ心を打つのか――90年代に求められた“リアル”
#Mr.Children #TOMC

前回より本連載では、1994~2000年頃の作品を中心に、Mr.Childrenのサウンドやアレンジ面、制作プロセス等に焦点を当てて語っている。第2回となる本稿では、『深海』『BOLERO』の制作から一時的な活動休止に至るまでの1995~1997年を軸に、サウンドのさらなる変化を追いながら、この時期の楽曲が持つ“特別な魅力”の謎を解き明かしていきたい。
<第1回はコチラ>
『深海』 “ヴィンテージ・サウンド”が映す、あるがままの姿
1994年、「innocent world」「Tomorrow never knows」とメガヒットを立て続けに放ったMr.Children。プロデューサー・小林武史の発案で始まった、ホテルのスイート・ルームを貸し切っての“ヒルトン・レコーディング”は翌年も続けられた。引き続き大ヒットを連発するさなかの1995年10月、桜井和寿はホテルで20曲あまりを集中的に制作しており、これらは翌年以降のアルバム『深海』(‘96)『BOLERO』(‘97)へと繋がっていく。
「名もなき詩」(‘96)を除いて、『深海』のレコーディングは、『Versus』(‘93)の一部楽曲でも使用されたニューヨークのウォーター・フロント・スタジオで行われている。この場所はアナログ/ヴィンテージ機材を愛する名物エンジニア、ヘンリー・ハーシュが切り盛りしており、レニー・クラヴィッツの初期作が録音された地として名高い。
60~70年代のソウル・ミュージックやジョン・レノンのソロ作から影響を受けたレニー・クラヴィッツのデビュー作『レット・ラヴ・ルール』(‘89)は、レコード会社との契約が決まる以前、レニーとヘンリーが意気投合してDIY的に制作された。シンプルながら楽器本来の“リアル”な魅力がはっきりと表れたそのサウンドは、デジタルリバーブを駆使した“ゴージャス”な80年代流の音作りとは対極にあるもので、70年代以前のサウンドが再注目される契機となった作品と目されている。
この場所で真っ先に録音されたのが「花 -Mémento-Mori-」であった。それぞれの楽器の音が太く逞しく録れないと成立しない、音数を選び抜いたアレンジが見事にハマった名録音である。
また、「ニューヨークでアナログ機材で録音する」という発想のきっかけになったという「虜」は、ブルースロックにR&B/ゴスペルの要素が入り混じった、彼らの長いキャリアでも屈指と言えるほどルーツ・ミュージックに根ざした表現が楽しめる。ハードな出だしの一音や、一気に左右のサラウンドを広げるような後半部のコーラス然り、音のダイナミズムや配置が絶妙で、非の打ち所がない仕上がりだ。
小林は当時の音作りについて「コンプをパツパツにかけて音圧を上げるのではなく、ひとつひとつの楽器のダイナミズムをしっかり捉えること、それこそがリアルだと思ってやっていた」という言葉を残しており、具体例として、「シーラカンス」で桜井の弾くレスポール・ギターをあえて小さいアンプで鳴らして録ったことを挙げている。こうしたサウンドを気に入った小林は、のちにYEN TOWN BAND『MONTAGE』(‘96)も同スタジオで制作している。
先述の通り「名もなき詩」だけは東京での録音だが、アルバムでは前後にインタールードや弾き語り調の「So Let’s Get Truth」が巧妙に配されていることもあり、違和感はほとんどない。また、録音に際しては、のちの『重力と呼吸』(‘18)制作時にも再来する「バンドの4人が見えてくる音にしたい」という方向性をメンバー全員が共有していたという。同曲を東京で録音したあと、ニューヨークでのレコーディングでもその思いが大切にされていたことは、アルバムの仕上がりを聴けば一目瞭然だ。
例えば「マシンガンをぶっ放せ」について、ギターの田原健一は「各楽器にしっかりとした配役があり、どの楽器も端役にはならないアレンジが成立している」という言葉を残している。『深海』はメンバー全員の魅力を余すことなく伝えてくれる、ロックバンドとして最も理想的なサウンドを持ったアルバムなのだ。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事