
手塚治虫からカレー沢薫まで……動物にも隠毛にもなる「漫画家の自画像」徹底分析
#インタビュー #漫画

漫画家が自身を描いた自画像、作中に作者自身が顔を出す楽屋オチや読者サービス、自伝マンガ、自分を主人公にしたエッセイマンガ、私小説のマンガ版である「私マンガ」、マンガ業界を描いたフィクションである「漫画家マンガ」、評伝マンガ、マンガの描き方マンガ……。こうした広い意味での「漫画家の自画像」を網羅的に扱い、分類し、歴史の流れを整理した労作『漫画家の自画像』(左右社)が刊行された。
漫画家は自己/漫画家をいかに描いてきたのか、そこから見える業界の変化とは──。著者の南信長氏に訊いた。

手塚治虫は「マンガの社会的地位を上げたい」
──なぜ、こういうテーマに興味を持ったのでしょうか。
南 もともとマンガが好きで、マンガの中に漫画家が出てくる楽屋オチ的なネタが好きだったし、「週刊少年ジャンプ」(集英社)の目次にある漫画家の近況欄や「漫画家のひみつ!」的な企画記事も好きだったんです。加えて、2000年代以降に「漫画家マンガ」が明らかに増えていると感じていたことがきっかけですね。
──西洋絵画の自画像と漫画家の自画像の比較をしていましたが、何が似ていて何が違いますか?
南 『自画像の美術史』(高橋達史/東京大学出版会)などの本でも言及されていますが、「自分を描く」とは「自分と向き合うこと」であり、自分の内面を掘り下げる「自己省察」の面と、自分をどういう形で表現するかという「自己演出」の面がある。それは漫画家の自画像においても基本的には同じです。ただ、画家の場合は自画像自体が作品になりますが、漫画家はそれ自体が作品になるわけではない。いかに自分というキャラクターを作るか。そこが違います。そういう意味では自己省察よりも自己演出のほうが大きいでしょうね。
──昔の漫画家は顔写真を出していたのが徐々に自画像に代わり、その自画像も人間の顔から動物になり、最近では無機物のようなよくわからないものになっていく、という指摘が面白かったです。
南 戦後、手塚治虫やトキワ荘の面々が活躍した時代は「マンガの社会的地位を上げたい」という想いがたぶんみなさんあって、文化人的な役割を担うためにオモテに出ていった。手塚先生をはじめトップの方々が顔を出しているわけですから、後輩も「出ろ」と言われたらイヤとは言えないところがあったと思います。
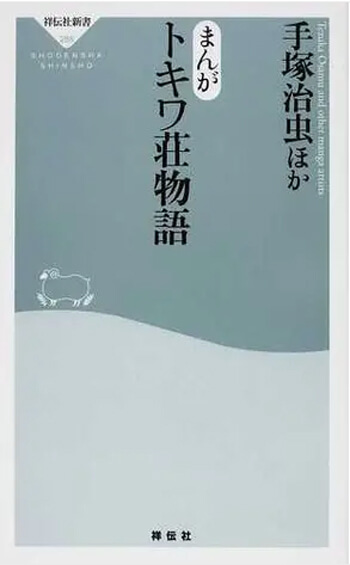
でも、そういう時代が過ぎて、マンガがサブカルチャーとしてある程度の地位を認められるようになった80年代頃から、漫画家の中にもある種の権利意識が芽生え、編集者も漫画家の意向をそれなりに尊重するようになり、ムリにオモテに出なくてもよくなっていった。顔出しなしで自画像のみの作家も増え、さらにはだんだんと人間じゃない自画像も許されるようになっていった。
──漫画家の社会的な地位の変化も、自画像の変化に影響があると。
南 それはペンネームに関しても同様で、昔は普通の人間の名前だったのが、80年代以降、人間離れした変わったペンネームが増えてきました。最初はエロマンガや同人誌系の作家が中心で、その人たちが一般誌に進出するのに伴って、そういう傾向が広がっていきます。
自画像の動物化、無機物化とペンネームの変化は、「匿名性を確保したい」ということからのパラレルな動きだと思っています。
──2000年代以降、漫画家マンガが増えていますが、つまり、漫画家はかつてよりも自分たちの身のまわりの世界を描くようになっているわけですよね。しかし、自分の顔や名前のような具体的な情報・属性については伏せようとしている。自分たちの世界を見せたがると同時に、自分のことは伏せたがる。何か乖離があるように感じますが……。
南 とはいえ、実録系よりも完全にフィクションの作品のほうが多いですからね。フィクションに関しては、あくまでも物語であって自分の話ではない。そこに作者の属性は関係ないですよね。また、大御所漫画家の自伝や、そのアシスタントだった方たちによる評伝・伝記などの実録系の場合は自分もキャラとして出るし、場合によっては「そこまで描くの!?」という赤裸々な描写もあるほどで、私はそこに不均衡な印象は持っていません。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事






