
大学の経営難、科研費の偏り、教員のブラック労働……日本の教育が“おかしい”のは文科省のせいか?

カネ(予算)がない、働いても給料がろくに払われない、しかし雑務と労働時間は増えていく――。小中高校の教育現場で、あるいは大学の研究環境に関しても、よく聞かれることだ。
その疲弊と不満の原因として「文科省が悪い」としばしばいわれるが、では文部科学省とは一体どんな特徴を持った役所なのか? なぜ予算は毎年減らされるのに小中高校や国立大学法人に対する締め付けは年々厳しくなっていくのか? それらの疑問を解き明かした『文部科学省 揺らぐ日本の教育と学術』(中公新書)の著者である東北大学大学院教育学研究科の青木栄一教授に、文科省や財務省、学校現場、保護者の問題点について訊いた。
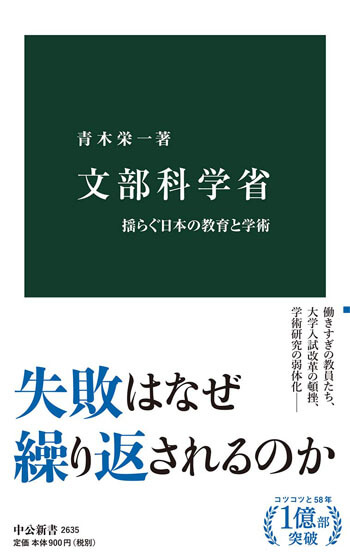
子どもの頭数で予算を確保する時代遅れの制度
――そもそも、なぜ財務省は文科省の予算、つまり国家による教育への投資を削り続けるのでしょうか? 教育に力を入れるほどGDPが増えるはずなのでは?
青木 まず、現状の初等中等教育の財政制度は「子どもの人数に応じて教員の数や人件費が割り出される」という「数」ベースになっています。この制度は、第2次ベビーブーマー(私はそのど真ん中の世代です)が在学していた1990年代初め頃までは、労せずして予算が増加していたので文部省(当時)にとっては最高の制度でしたし、当時は教員の給与水準や社会的ステイタスもなかなかよかったんです。文科省は、そのときの成功体験から抜け出せずに、新しい仕組みを生み出そうとしていない。ところが、少子化になると自動的に予算が減っていく。財務省からすればこれはありがたいので、現行制度が放置し続けられているわけです。
しかし、もはやこのやり方でうまくいかないことは明白です。例えば、集団生活になじめない子、外国籍の子、家庭状況が困難な子たちを守るためには、人手が必要です。にもかかわらず、今の日本の制度では文科省予算の用途が先生の雇用に偏っている。学校にはそうした子どもたちをケアする専門職が必要なのに、国の予算では雇用できない。だから、市町村が自腹を切って特別な教育ニーズを持つ子たちの支援員などを雇用しています。子どもの頭数で予算を確保して回すモデルから、「今、本当に必要なものとはなんだろう?」ということに立ち返って考え直すべきです。
――一方で、大学はどうでしょうか?
青木 『文部科学省』で扱った国立大学に関してもそうですが、入学する学生のほとんどは高校卒業して間もない10代の若者です。少子化が進んでいる日本の大学は18歳人口が減少することで経営危機に見舞われているという見方が大勢を占めています。
しかし、他国では大学に入学する学生の年齢層は20代後半くらいまで幅広くいますから、日本も同じように「知識は陳腐化するのだから、何歳になっても学び直しをする人を増やそう」という発想になっていれば、そこまで問題が深刻にならずに済んだはずです。ところが、日本では企業による新卒一括採用の弊害もあって、財務省も文科省も年齢主義にとらわれ、「18歳人口が減る=国立大学はこんなにいらない」になる。初等中等教育と形はやや違いますが、主要顧客である、高校を卒業したばかりの18歳の「数」に振り回されてしまう。
――私は社会人になってから修士課程に入りましたが、まわりに「海外と取引していると、向こうでは修士・博士が当たり前で恥ずかしくなった」「せめてマスターくらい持っていなければ勝負できないと痛感したので来た」という人はわりといましたね。MBAを持っていないとマネジメント層になれない企業もアメリカなどではザラにありますし。
青木 日本では企業も「学部新卒で、陽キャなら良し」という風潮がありますが、実際には海外とやり取りした途端、「それだけでは勝てない」と気づく人も多い。そこは変えていけるはずなんです。
法人化した国立大学に国の介入が強まる謎
――青木さんの本では、文部省と科学技術庁の合併の後に高校や大学への介入が非常に強まったことが書かれていて、目から鱗が落ちました。高等教育(大学教育)では2004年度に国立大学が法人化され、そうなってから大学に対する介入が強まったそうですね。「法人化して組織形態が企業の経営体に近くなれば独立性は高まるはずなのに、なぜ国からの介入が強まるのか」は、外から見ると不思議な点です。
青木 国立大学は法人化されて以降、文科省から年間1%ずつ予算を削減される一方で、制度的な縛りもあって自己財源から収益を上げることがあまりできませんでした。さらには、寄付金を必死に集めることをしてこなかったがために、文科省依存が加速していきました。
例えば、私が勤める東北大学は学部と大学院合わせて年間約5000人が卒業・修了します。その卒業生たちが平均して年に1万円寄付(わずか1日27円、1週間192円)を続けてくれたら、大学全体で1学年で年間5000万円です。法人化して間もなく20年になりますから、20年目の寄付金は全部で10万人、つまり1年で10億円になる計算です。これは、文科省が国立大学を競争させるために実施しているスーパーグローバル大学創成支援事業の約2倍の金額です。
つまり、ごくささやかな寄付文化を根付かせてさえいれば、年間たった5億円のニンジンをぶら下げられて、大学トップをはじめとして研究者たちが大変な苦労をしてまで振り回される必要はなかったはずなんです。
また、弁護士であれば相談料として1時間何万円か取るわけですけれども、文系の先生方は役所からの仕事にしてもなんにしても無給・薄給で受けてしまう。いわばコンサル業として、自らの専門知識や経験をはじめとして、商品として売れそうなものを開拓することも怠ってきてしまった。
しかし、法人化で文科省から切り離されたという大枠はつくられてしまいましたから、全体として地盤沈下しても文科省は守ってくれず、大学間の格差が広がっていく現状を招いてしまいました。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事






