
あの話題作のヒロインらはこうして口説かれた 映画プロデューサー奥山和由が語る「女優たち」
#インタビュー #奥山和由 #女たち
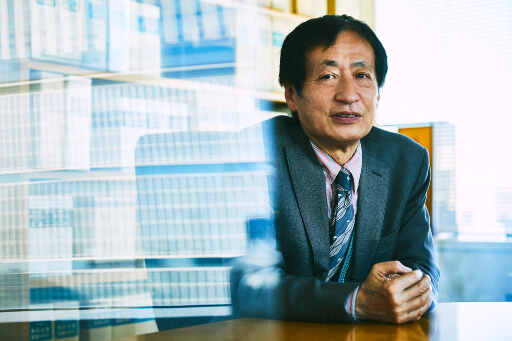
実録犯罪映画の金字塔『丑三つの村』(83年)、ビートたけしが暴力刑事を演じた北野武監督デビュー作『その男、凶暴につき』(89年)、深作欣二監督のアクション快作『いつかギラギラする日』(92年)、世間からはみ出した負け犬たちの逆襲劇『GONIN』(95年)……。どれも閉塞感漂う社会に風穴を開けようとするアウトローたちの生き様、死に様を鮮烈に描いた人気作だ。
そんな時代を先取りしたような画期的な映画を次々と生み出してきたのが、映画プロデューサーの奥山和由氏。コロナ禍によって閉塞感がいっそう増した現代社会を生きるヒロインたちを映し出した最新作『女たち』の劇場公開が6月1日(火)より始まる。
「女優が燃え上がることで、映画は美しくなる」と語る奥山プロデューサーにコロナ禍での映画製作、さらには過去の話題作や噂にもなった女優たちをめぐる逸話の数々を振り返ってもらった。
――最新作『女たち』は、『罪の声』(20年)や『ミセス・ノイジィ』(21年)などで注目を集めた篠原ゆき子と、久々の映画復帰となった高畑淳子の“母娘”バトルが強烈なインパクトを与えます。養蜂場のある小さな田舎のコミュニティーを舞台に、主人公の美咲は母親の介護に加え、雇用や結婚をめぐるトラブルに揺さぶられ、精神的に追い詰められていく。奥山プロデューサーが松竹時代に手がけた『丑三つの村』を彷彿させるものを感じますが……。
奥山 いやいや、『丑三つの村』とはまったく違います(笑)。確かに僕はこれまで時代に逆行するような映画ばかり撮ってきました。でも、今の時代をきちんと映し出した映画を、そろそろ作ってもいいんじゃないかと思うようになったんです。小津安二郎監督の『東京物語』(53年)も、黒澤明監督の『七人の侍』(54年)も、フランシス・F・コッポラ監督の『ゴッドファーザー』(72年)も、製作された時代の空気を映し出しているわけです。そして、「時代を創っていくのはいつも女性だ」と僕は考えています。男たちが小狡くなって、忖度社会を生み出す中で、本音で生きる女性たちを描こうということです。
篠原ゆき子さんは『共喰い』(13年)などでも素晴らしい演技を披露している女優だけど、僕がプロデュースした『銃2020』(20年)ではレイプされた挙げ句に射殺されてしまうヒドい役をやらせてしまった(苦笑)。それもあって、彼女の魅力が充分に発揮できる主演作をと考えた。一方、『おだやかな日常』(12年)を撮った内田伸輝監督のことも気になって、久しぶりに声を掛けたところ、ちょうど篠原ゆき子主演作を練っていた。そこで動き始めた企画なんです。
――本作の撮影は2020年7月で、製作は新型コロナの感染拡大でふたたび緊張感の高まっていた時期になります。どのようにして製作を進めたんでしょうか?
奥山 台本の読み合わせは禁止、ラブシーンは避けるなど、コロナ禍での映画制作のガイドラインは、まるで禁酒法のように厳しい内容でした。都内での撮影は無理でしたが、幸いにも群馬でロケ地が見つかりました。
障害を持つ母親役の高畑さんは、実際に半身不随になっている方に会って取材したいということでしたが、施設などを直接訪問することは不可能だったので、リモート取材をしてもらいました。オンラインでの取材でしたが、高畑さんは脳に刷り込むようにして、障害を持つ方の動きを身につけたんです。モスクワ映画祭の記者会見で「母親役の女優は本当に障害を持っているのか?」と質問されるほど迫真の演技を披露しています。
脚本に関しては、内田監督が書いた初稿段階では養蜂場が存続するかどうかを最後は住民投票で決めるというものになっていたので、「物語の終わりが合議制だなんて、そんな映画はあり得ない!」と何度も書き直してもらいました。最終的には、女優たちがそれぞれ抱えている感情を吐き出すようなエチュード形式のものにしています。結果的に内田監督が本来得意とするスタイルになったんです。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事






