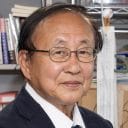強盗犯を愛してしまう人質の奇妙な心理とは? 実録犯罪ドラマ『ストックホルム・ケース』
#映画 #ハリウッド
ボブ・ディランを口ずさむ犯人たち

是枝裕和監督がフランスで撮った『真実』(19)やリチャード・リンクレスター監督の『6才のボクが、大人になるまで。』(14)など、イーサン・ホークはだらしないけど、憎めないオジサン役が似合うようになった。本作を撮ったロバート・バドロー監督の前作『ブルーに生まれついて』(15)にも主演しており、薬物中毒に陥ったトランペット奏者のチェット・ベイカーを好演している。女性からしてみれば、ダメ男のほうが母性本能をくすぐられてしまうのだろう。SF映画『プロメテウス』(12)でタフなヒロインを演じたノオミ・ラパスとの相性も悪くない。
コメディのような笑いを誘うシーンが本作には多い。ビアンカと共に人質となっていた女性行員のクララ(ビー・サントス)は、事件のストレスで予定よりも早く生理が来てしまう。銀行内には生理用品がないため、ラースは慌てて警察に生理用品を持ってくるよう要求する。クララ本人よりも、ラースのほうがパニックになってしまう。
金庫室の扉を開けるシーンでは、ラースは持っていた銃が邪魔になり、人質に「ちょっと持ってて」と銃を渡す。扉が開いたら、人質は銃をラースに返す。おいおい、と言いたくなる。まるでコントのようなやりとりだ。
夜が更け、ラースとグンナーはボブ・ディランの曲「明日は遠く」をデュエットする。銀行に立て籠り中に、呑気にボブ・ディランを歌ってみせる強盗犯たち。プライドや対外的な体裁にこだわる警察が催涙ガスを打ち込む準備を進める間、ラースと人質たちは心の距離が近づいていく。
「ストックホルム症候群」という言葉を有名にしたのは、この事件の翌年、1974年に起きた米国の“新聞王”ウィリアム・ランドルフ・ハーストの孫娘パトリシアが誘拐された事件だ。裕福な生活を送っていた女子大生のパトリシアは左翼系ゲリラに誘拐されるが、「カリフォルニアの貧民6万人に食料を用意しろ」というゲリラたちの要求に共鳴し、彼らと共に銃を手に銀行を襲撃するようになる。
パトリシアはゲリラによって一時的に洗脳されていたのか、それとも自分から進んでゲリラの仲間になったのかは定かではない。逮捕されたパトリシアは「仲間になったふりをしただけ」と演技だったことを主張し、特別恩赦によって釈放された。その後、パトリシアは女優デビューを果たし、変わり者好きなジョン・ウォーターズ監督の『I LOVE ペッカー』(98)などに出演している。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事