
みんなニューヨークが好きだったんだな……アーウィン・ショー『夏服を着た女たち』
#雑誌 #出版 #昼間たかしの「100人にしかわからない本千冊」
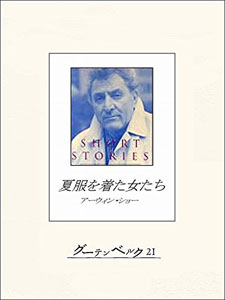
今はそれほどでもないだろうが、1980年代前半の一時期、日本人にとってニューヨークは、憧憬を抱かせる特別な街であった。
「であった」と生意気に書いてはみるが、筆者も入浴には毎日親しんでいるものの、ニューヨークというのが、どんなところだかは訪れたことがないので知らない。
ただ、文化的にも洗練され、日本よりも先進的なオシャレな街・それが日本人の抱くニューヨークのイメージであった。
その憧れはいわば、まだ鮮明に残っていた敗戦の記憶。それが克服されるのはバブル景気を待たねばならないが、とにかくニューヨークへの日本人の関心は高かった。
筆者の本棚をパッと見てみると「ニューヨーク」をタイトルに使っている本が何冊も。
『ニューヨーカー物語』『ニューヨーカー・ノンフィクション』『ザ・ニューヨーカーセレクション』『ニューヨークは闇に包まれて』『ニューヨーク・スケッチブック』……筆者の趣味趣向で偏っているが、よくもまあ、こんなに「ニューヨーク」というタイトルをつけたものである。
そうした都市を描いた作品で、今回取り上げたいのは、アーウィン・ショー『夏服を着た女たち』(講談社)である。
この短編集、邦訳は複数あるが、原題に忠実に『サマードレスの女たち』としているものもある。でも、やはり『夏服を着た女たち』のほうがいい。これは、今は無き翻訳者にして、ニューヨークの紹介者・常盤新平の妙技である。
アーウィン・ショーは数多くの作品を残した小説家なのだが、日本語版ウィキペディアの記述を見ると、こんな解説が。
===
短編も多く、「夏服を着た女たち」はしゃれた短編として日本でもしばしば話題にのぼる。
===
こんな解説を読むと、どこかスカした感じのスノッブな作品かと思えるが、そうではない。
オシャレな都会の風景を描いたフリをしながら、読後に残るのは無常観。
常盤新平の手により描写されるニューヨークの風景は、時代が違うとはいえ、実際見てきて書いているからこその輝きがある。でも、その輝きに照らされる男女の人生は常に悲哀ばかりである。
収録作「80ヤード独走」の主人公の物語は、いわば転落の人生。アメリカンフットボールのスター選手として、大学生活を過ごした主人公は、恋人と結婚し、恋人の父親の会社で形ばかりの仕事をして享楽的な日々を送る。だが、父親の破算と共に、その生活も終わる。働きに出た妻は、みるみる出世していくが、過去の栄光を捨てられない主人公は混迷を深める。
「愁いをふくんで、ほのかに甘く」は、かつて互いに想い合った女優の卵だった恋人との再会と別れの物語。
どちらの作品も、夢やぶれたり、絶望に打ちひしがれた男女は華やかな都会を去っていく。いかに文体はオシャレでも、そこに描かれる物語は重く悲しい。
邦訳された当時、ここに日本人が何を思ったかは、わからない。
21世紀の今、改めて読んで思うのは、どこに住もうとも人生の悲哀は必ずあるということ。
でも、それを、しゃれた文体で書くことができるアーウィン・ショーと、さらにしゃれた感じに翻訳できる常盤新平は、やっぱりスゴイのだ。
いま、ネットの普及により文字を目にする機会はずっと増えているけど、都市に生きる人々の言葉は殺伐としている。でも、昔は殺伐としていなかったわけじゃあないだろう。
せっかくだから、しゃれた感じで気取っても、本質がずれなければ、むしろいい。
(文=昼間たかし)
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事






