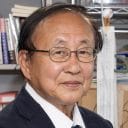エビデンスがなくても疑問を忘れるな。「ユリイカ」1988年11月号
#雑誌 #出版 #昼間たかしの「100人にしかわからない本千冊」

もはや、物書きの世界でも、竹中労の名前を出すと「誰?」であり、沢木耕太郎は「ああ『深夜特急』の人」である。
知らない、読んでいないは構わない。大切なのは「こういう人物が書いた、こういう作品なのです」と話した時に、ピンとくるかこないか。それは「考えるな、感じるんだ」の世界。言葉を用いる仕事だが、言葉以前の部分で合わない人とは、会話する時間も億劫に思えてくる。
読んでいなくても「おお! 過去にはそんな作品が」と食いついてくるようなタイプの人。そこまではいかなくても、こちらの提示するベースにある世界観を信頼してくれる人とは、物書きの仕事はやりやすい。
そこには、小さな仕事でも、それを大勢の人に読んでもらい、あわよくば将来も残る作品にしたいという想いがある。
でも、将来に残る作品というものは難しい。そう思ったのは「ユリイカ」1988年11月号(青土社)の特集「アメリカン・ノンフィクション」を読んだ時のことである。
この特集がテーマにしているのは、前にこの連載でも触れたニュージャーナリズムの総括である。トム・ウルフやゲイ・タリーズなどの短編を収録する特集で、川本三郎は「ベトナム戦争があったからこそ……」という文章を寄せてニュージャーナリズムの起源と発展を記している。
その中で川本は「ジャーナリズムは駆け足のメディアである」という。
作家も、アカデミズムの学者たちも捕らえきれない、現代の最前線を、とりあえずジャーナリズムがつかみとる。
原文では「とりあえず」の部分に傍点が記されている。この意味をどう考えればよいのか。私は、自身の思いのままに、躊躇することなく取材して、勢いよく書くことなのだと思っている。
でも、それは適当なことをやってもよいという意味では決してない。
昨年末に「朝日新聞」の論説委員が「エビデンス? ねーよそんなもん」と、発言したとかしないとかで物議を醸した。この論説委員の著書を読むに、言葉の意味は、何か気味の悪さを感じて政権批判をする自分の信念にエビデンスがない、ということなのだとわかった。多くの批判者が「新聞記者が裏取りもせずに書くのか」という言葉をぶつけていた。それに対して、著書の引用を用いて「意味をちゃんと考えろ」という反論がなされたわけである。
でも、感情の赴くままに批判するのであれば、余計にタチが悪いなと思った。
もし、物書きを矜恃にするとしているのであれば、まったく足りない。気持ち悪いから、気持ち悪いと書くだけでは単なる落書きの類いと違いはない。
ベースに必要なのは「なぜ」という疑問である。
「なぜ、自分はそんな感情を抱いてしまうのか?」
出来事や人物に、説明できない嫌な気持ちが湧く理由を探究する気にならないなら、ジャーナリズムではないと思うのだ。
そうしたベースもなく「エビデンス? ねーよそんなもん」などと乱暴な言葉を吐いてしまう背景にあるのは、劣化である。
そんな時に読み直す、特集「アメリカン・ノンフィクション」は新鮮だ。収録されているウルフやタリーズの短編は、多くの人が考えているジャーナリズムの概念を徹底的にたたき壊す。
大抵の人は、ジャーナリズムという枠で書かれる文章というものは、こんな構造でできているように思っている。
でも、これは一種、わかりやすく手を抜くための方法に過ぎないのではないかと思う。
ノンフィクションやルポルタージュというのは、既存の概念の破壊をも使命にしている。ならればこそ、書き方も既存のものには囚われない、最初が叫び声から始まっても構わないし、ムカついてアイスを食べてもよい。ただ、なぜそうなったのか。それを考えることを忘れては成立し得ない。
(文=昼間たかし)
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事