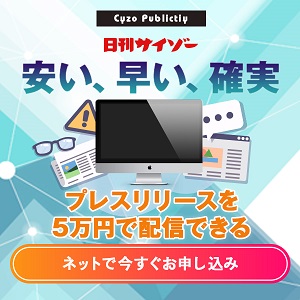『ローグ・ワン』『キングスグレイブFF15』に見る、「不気味の谷」をめぐる戦い
#オワリカラ #偏愛文化探訪記
しかし、何よりも見慣れている「自分自身」でもある人間の顔や動きは、まだまだ違和感なく描くのは途方もない労力と資金がいる大変なことだ。
たとえばピクサーの作品が、基本的にキャラクターをデフォルメしているのにも、この「不気味の谷」の影響がある。実は初期のピクサーのプロトタイプの作品は、ちょっとキャラクターがリアルで不気味だったのだ。その反省から、どこまでCGをリアルにすると人は嫌悪感を覚えるかを注意深く検討し、デフォルメされ完成されたのが、ピクサーのキャラクターなのだ。
一説には、ボードに無数のCGキャラクターの写真を貼り、どこから不気味に感じるかをリサーチしたそうだ。ある意味、ピクサーは不気味の谷の最強の攻略法を実践している。「そもそも谷を越えない」という「勇気ある撤退」を選択したのである。この方法は、今ではフルCG映画の主流にまでなっている(要するに、アニメの3DCG化だ)。
しかし、今回の『ローグ・ワン』のように、実在の役者と絡ませたりできる、実写を再現したような人間キャラクターを描こうとする場合、どうしても「不気味の谷」を越える完璧にリアルな人間のCG表現が必要になる。それでは、誰かが真っ向から不気味の谷に挑戦するしかない。戦争だ!
さて正直、結論からいえば、今でもほとんどのフルCGで描かれた人間のキャラクターは不自然だ。ターキン提督も正直、ちょっと不気味であった。たとえば『ジャングル・ブック』が動物や風景はすべてフルCGで表現したのに、主役の少年や登場人物だけは実写を採用した理由のひとつには、その表現の困難さがあるだろう。ここ10年ほどのCG技術というのは、日本よりはるかにハリウッドのほうが進んでしまったといわれている。
特に数年前のある時期から、巨額の資金を投じ続け驚異的な進化をしたハリウッドのCG技術と日本映画のCG技術の間に、簡単には越えられない圧倒的な「壁」ができてしまったという話を聞いたことがある。そんなハリウッドでも、人間をフルCGで描く映画は、そう簡単には作れない。単純に、映画1本分の人間キャラクターを違和感なくフルCGで描く労力と資金を考えると、生身の役者を使った方がいろいろ楽でよい、というのもあるだろう。
さらにアメリカは、役者の権利などにものすごく厳しい国だ。たとえば、フルCGの役者が簡単に使えるような世界になると、本物の役者は失業してしまう、というので、アメリカでは人間をフルCGで描くことに、映画俳優組合(SAG)からクレームがつくというウワサも聞いたことがある。
「え~、そんなバカな!」とも思うけど、これは、音楽業界でもあった話だっていうから驚きだ。70年代、初めて「コンピューターで打ち込むドラム」が登場した頃は、全米ドラマー組合みたいなところから「生身のドラマーの仕事がなくなる!」というクレームがついて「打ち込みのドラムを使うときは、生身のドラマーをアドバイザーとして雇うべし」という、ものすごいバカみたいな暗黙のルールが誕生したという。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事