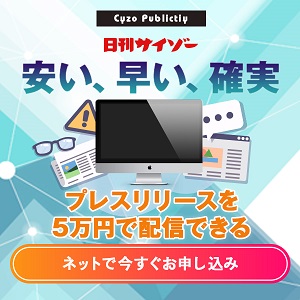『ローグ・ワン』『キングスグレイブFF15』に見る、「不気味の谷」をめぐる戦い
#オワリカラ #偏愛文化探訪記
みなさんは「不気味の谷」をご存じですか?
「そんな怖い谷は、わたしの地元にはありません!」って、僕の地元にも、そんな王蟲やモルボルが生息してそうな谷はありません。
これ、CGとかロボットの業界で、2000年代から使われるようになった言葉だ。もともとは1970年代に日本人のロボット工学者が提唱した概念で、それが近年になって海外でも頻繁に使われるほどポピュラーな言葉になった。
そして今、この「不気味の谷」をめぐる戦いが熱い!
この「不気味の谷現象」は簡単に説明すると、「ロボットの姿や動きを人間に似せていくと、リアルになるにつれて、それを見た人の好感度や親近感が高まっていく。しかし、ある一定よりリアルさが高まった瞬間、ものすごく不気味に感じてしまう現象」のこと。
つまり、中途半端にリアルなものが一番不気味、ということだ。
また、この現象は「そこから、さらにリアルさを増していってほとんど人間と区別できないレベルに達すると、嫌悪感が一気に反転して好感に転じる」という特徴もある。
この好感度の動きをグラフで描くと、リアルさが一定レベル以上に高まるとグイーンと急降下して嫌悪ゾーンに突入して、さらにリアルになって反転してグイーンと急上昇するまでが「谷」のような極端な線を描くため、「不気味の谷」と名付けられたのだ。
まず、はっきり言おう。ネーミングセンスありすぎ博士! いや、天才か!
不気味の谷、かっこよすぎる。中2の頃に住みたかったものだ。
で、そんな願望はともかく、この言葉が近年になってにわかに多用されているのは、この現象がCGで描かれた人間にも当てはまるからだ。
みんなも見覚えがないだろうか? すっごくリアルで不気味なCGキャラクター。または、めっちゃリアルなのに、動きが異様に不自然なCGキャラクター。こうしたキャラクターたちは不気味の谷を越えられず、その谷底に消えていった犠牲者であったといえる。
そうなのだ、世界の映画やゲームのCGの世界でのここ10年くらいは、この「不気味の谷」をいかに攻略するかの戦いだった。
折しも2016年は、動物キャラクターたちをフルCGで描いた海外映画『ズートピア』『ペット』『ファインディング・ドリー』、人間「以外」をすべて完璧なフルCGで描いた『ジャングル・ブック』が大ヒット。さらに日本産でも、リアルなゲーム発の完全フルCG映画『KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV』なんかが公開され、世はフルCGの春真っ盛りだ(秋だけど)。
CGの世界において、無機物はかなり早い段階で違和感のないレベルでの描写が可能になった。人間以外の動物も、もはや実写で実際にそこにいるのと区別つかないレベルに達しているのは『猿の惑星:新世紀』や『ジャングル・ブック』を見ているとわかる(超すごい)。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事