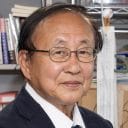高倉健が淹れたコーヒーは実は美味しくなかった!? 人格者ではない“昭和のスター”の人間くさい素顔
#映画 #インタビュー #高倉健
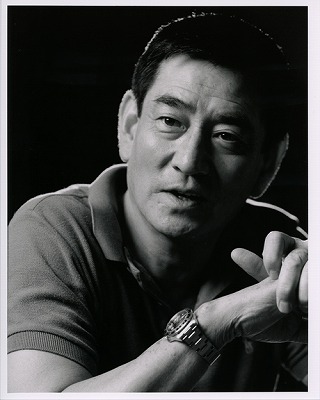 “最後の映画スター”高倉健。これまであまり語られることがなかったが、海外からも様々な出演オファーが届いていたことが明らかになっていく。
“最後の映画スター”高倉健。これまであまり語られることがなかったが、海外からも様々な出演オファーが届いていたことが明らかになっていく。スクリーンの中のこの人に何度励まされたことだろう。この人の映画を観る度に、自分の抱えている悩みはとてもちっぽけなものに思えた。到底手が届かないスターとしての風格を備えながら、でも遠い親戚のような親しみやすさも感じさせた。この人がいなくなって、本当に淋しい。2014年11月10日に映画俳優・高倉健が亡くなって、もうすぐ2年になる。男女を問わず、誰もが憧れた“昭和の大スター”高倉健の魅力を検証した初のドキュメンタリー映画が『健さん』だ。『ブラック・レイン』(89)で共演したマイケル・ダグラス、長年にわたって手紙でのやりとりを重ねていたマーティン・スコセッシ監督、高倉健への憧れから『君よ憤怒の河を渉れ』(76)のオマージュ作を製作中のジョン・ウー監督ら海外のビッグネームたちに加え、実妹の森敏子さん、元付き人の西村泰治氏ら総勢20人以上がそれぞれの心の中に今も生きている高倉健について語っている。
本作を撮ったのはNY在住、写真家として活躍する日比遊一監督。俳優としてのキャリアも持つ日比監督は高倉健の大ファンだったが、生前の高倉健とは直接的な交流はなかった。言ってみれば本作は、海外在住歴の長いひとりの日本人クリエイターが、映画俳優・高倉健の中に失われつつある日本人像、日本人の美意識を見出し、その残像を追い求めたものとなっている。
日比遊一「僕が日本を出て、米国に渡ってもう30年になります。昭和から平成に変わる頃でした。ある意味、日本で暮らしている日本人以上に僕は日本人っぽいと思うことが多いんです(笑)。今の日本人は昭和の日本人の美しさを忘れかけているように、僕には思えるんです。昭和の日本人の美しさって、高倉健さんの美しさでもあるわけです。昭和を生きた男・高倉健さんのかっこよさを多くの人にきちんと伝えたいという想いから、この映画を撮ったんです」
 NYから帰国した日比遊一監督。「高倉健さんの俳優としての評価をきちんと伝えるものを残したかった」と語る。
NYから帰国した日比遊一監督。「高倉健さんの俳優としての評価をきちんと伝えるものを残したかった」と語る。日比監督は名古屋出身の1964年生まれ。高倉健の代表作『昭和残侠伝』シリーズが始まったのが1965年だから、高倉健の人気が爆発した任侠映画の全盛期をリアルタイムで体感したわけではない。高校卒業後に上京し、新宿駅南口にあったヤクザ映画専門館「昭和館」などに通い、東京でひとり暮らしを始めた日比監督は唐獅子牡丹を背負った高倉健の姿に魅了されていった。
日比「高校まではずっとスポーツひと筋で過ごし、あまり映画は観たことなかった。それなのにTVドラマ『探偵物語』に主演していた松田優作さんに憧れて上京し、日活の俳優養成学校(日活芸術学院)に入ったんです。学校ではロバート・デ・ニーロ派とアル・パチーノ派に分かれて演技論が飛び交っていたけど、僕はちっとも理解できなかった(笑)。それでオールナイト上映をやっている映画館に通って、浴びるように映画を観ているうちに、高倉健さんが主演している任侠映画の大ファンになったんです。当時は新宿の昭和館の他にも、池袋や鶴見にも任侠映画を上映している映画館がありましたね」
松田優作への憧れも冷めることなく、日活の撮影所に松田優作が現われたと聞くと、「弟子にしてほしい」と本人に頼み込みに行った。このとき、弟子入りは断られたが、松田優作から掛けられた言葉が、日比監督の生涯を大きく変えることになる。
日比「優作さんに『俺がお前くらいの年齢なら、米国に渡っている』と言われ、その言葉を真に受けて、渡米したんです。若気の至りってやつですね(笑)。すぐには英語が話せなかったので苦労しました。そんなとき、日本から持ってきた高倉健さんの主演映画をビデオで見たり、健さんが書いた本を読むことで元気をもらっていたんです。健さんは僕にとってバイブルみたいな存在なんです」
この頃、日比さんが観ていた映画は、『昭和残侠伝』シリーズや『網走番外地』(65)に『冬の華』(78年)といった硬派な作品。映画の中で懸命に耐える健さんに励まされながら、日比監督は一本気な性格のまま米国で根を降ろすことに。
日比「俳優として渡米したものの、ハリウッドでもNYでもなかなか仕事はなく、日本と米国を行き来していました。『波止場』(54)や『エデンの東』(55)を撮ったエリア・カザン監督が第2回東京国際映画祭のゲストで来場していたことから、下手なりに懸命に自分の想いを綴った手紙を送ったところ、カザン監督はとても親切な人で、『米国に来たら訪ねて来い』と返事をくれたんです。それで本当にお邪魔して、3カ月間ほど自宅に居候させてもらい、いろんなことを学ばせてもらった。しかもアクターズ・スタジオの共同設立者ロバート・ルイスを紹介してもらい、彼に弟子入りして7年間ほどアクターズ・スタジオで勉強させてもらったんです。その間、デニス・ホッパーに僕が撮った写真を褒められたこともあって、写真も撮り続けていたら今では写真家としての稼ぎのほうが多くなりました(笑)。でも、写真はあくまでも映画を撮るための絵コンテの勉強のつもりで、自分からは写真家と名乗ったことはない。映画への憧れはずっと変わらず持ち続けたんです」
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事