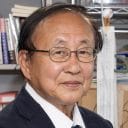自ら「グル」になろうとした中沢新一ら研究者たちの罪と罰
#宗教 #インタビュー #オウム真理教 #麻原彰晃
オウム真理教による地下鉄サリン事件から、今年で16年が経過した。15年の節目には各出版社もオウム問題を総括すべく、書籍の刊行や雑誌で特集を組むなどしたが、大きな反響もなく、もはや事件は風化したというのが現実ではないだろうか。しかし、オウム真理教が起こした地下鉄サリン事件は、いまだにきちんとした総括が行われているとは言いがたい。宗教学者の大田俊寛氏は、今年3月に出版された『オウム真理教の精神史 ロマン主義・全体主義・原理主義』(春秋社)において、宗教学者の責務を果たすべく、オウム事件の総括を試みた。今回、その大田氏と、元オウム真理教幹部でアーレフ(現アレフ)の元代表でもあった野田成人氏に対談を行ってもらった。野田氏自身、事件を総括すべく、昨年オウム真理教とアーレフ時代の出来事を克明に綴った『革命か戦争か オウムはグローバル資本主義への警鐘だった』(サイゾー)を上梓している。オウムという存在を、内側と外側から考察してきた2人の言葉から見えてくるものとは?
――野田さんは昨年『革命か戦争か』を出版されましたが、やはり地下鉄サリン事件から15年が経過して、あらためて事件を総括したいとお考えになったのでしょうか?
野田成人氏(以下、野田) 昨年、『革命か戦争か』を出したときには、私はすでにアーレフを辞めさせられていました。事件に関しては、元オウムの幹部としては、平謝りするしかありません。ただ、オウムの中でもいろいろな問題がありましたが、世の中を見ていて、日本社会の構造の問題について書いてみたいと思いました。
――日本社会の構造の問題というのは?
野田 例えば、非正規雇用の問題であったり、他には僕が学生の頃はコンパが盛んに行われ、酒を一気飲みさせられたり、頭から酒を浴びせられたりしました。こんなことの何が楽しいのかとあきれていました。ちょうどバブルの真っ只中だったこともあり、世間はお金と物であふれていました。そういった物質主義的なところに違和感を覚えていたのも確かです。
――大田さんは以前に「グノーシス主義」を研究されていますが、グノーシス主義とは何でしょうか?
大田俊寛氏(以下、大田) 一言で言えばグノーシス主義とは、紀元二世紀頃、初期キリスト教に発生した異端的宗派のことです。しばしば「キリスト教の最初にして最大の異端」とも呼ばれています。
――グノーシス主義やキリスト教神学の研究から、今回出版された『オウム真理教の精神史』のように、考察の対象がオウムという現代宗教へ移ったのはなぜですか?
大田 グノーシス主義をテーマに博士論文を書き終え、非常勤講師として大学の教壇に立つ頃には、私は、宗教学は人文社会系の諸科学の中でも、とても重要度が高い学問であると考えるようになっていました。その理由は、人間が作る社会というのは、必ず何らかの「信用」や「信仰」を基礎にして成り立っているからです。例えば現代の資本主義では、それ自体としてはただの紙切れでしかない「貨幣」という存在への信用や信仰を中心に、社会が成り立っている。社会の構成要素には、必ず信用や信仰の次元が存在します。そして宗教についての学というのは、社会の中心にどのような「信仰」があるのかということを第一義的に明らかにするための学問である。ゆえに本来、社会科学の最も根幹にあるべき学問であると考えています。
ところが、現在の宗教学を見てみると、地下鉄サリン事件当時、東京大学の宗教学の先人たちがひどい振る舞いをしてしまったこともあり、まともに物を考えることができる人であれば、日本の宗教学者の言うことには耳を傾けようとしないという状況が続いています。サリン事件以降、宗教学者は完全に社会的信用を失ってしまったわけです。一方で宗教学の中では、宗教学はディシプリンを必要としない「ゲリラ学」であるといった、根本から誤った認識がいまだに拡がっており、私はこうした考え方が、オウム事件を後押しすることにつながったのではないかと考えています。私自身、一人の研究者として、宗教学の再構築に携わりたいと思っているのですが、その第一歩として、オウム事件を学問的にどう捉えることができるかということをあらためて問題にしてみたいと思いました。
 野田成人氏。
野田成人氏。――今回の対談にあたって、お互いの著作を読んできていただいたのですが、率直な感想はいかがでしょうか?
野田 大田さんの『オウム真理教の精神史』を読んで大変興味深く思ったのは、オウムに対しての今までの批判というのは、オウムは仏教でもチベット密教でもないただの異端であるとか、その異端が勝手にサリン事件を起こしたのだというものが多かった。しかし大田さんは、オウム事件の背景には、近代の体制において、死を扱う宗教というものを私的領域に追い込んでしまったという構造的問題が存在すると言っています。私は、資本主義が生んだ構造的問題からオウムにアプローチしていますが、オウムという存在が、社会が抱えている構造的な矛盾からにじみ出てきたものであると見る点で、共通の捉え方ができるのはないかと思います。そういうことを宗教学者の立場から言っていただけるとありがたいです。
――大田さんは野田さんの『革命か戦争か』を読んで、どう思われましたか?
大田 オウム真理教の元信者によって書かれたこれまでの著作は、地下鉄サリン事件がどのようにして起こったのかというところで終わっているものが多かった。しかし野田さんの著作では、地下鉄サリン事件の後、教団がどのような紆余曲折を経たのかについて書かれている。具体的には、教団内において麻原信仰への回帰の動きが見られることや、アーレフ内における松本家の支配体制の在り方、そして最終的に野田さんがそこから排除される過程についてなどが克明に記されており、その点でとても価値のある本だと思います。
野田 大田さんの本の帯の、「近代の暗黒面を暴く」というのはいいですね。
大田 この言葉は、編集の方が考えてくれました。野田さんの本では、近代に発展してきた資本主義のシステムが背景にあって、資本主義から排除されたものが巡り巡ってオウムのような集団になったという分析が見られるので、「近代の暗黒面を暴く」という視点において、私の著作と共通性が見られると思います。私自身はこれまで、グノーシス主義やキリスト教教義史といった分野を研究してきましたので、宗教現象を見るときに、そこにある理念や教義が、いつ頃現れてどのように発展していったのかということを歴史的に考えてみるということが、体質として染み込んでいるところがあります。95年以降、オウム真理教に関する論考は膨大に発表されましたが、しかしそれらはどれも歴史的な視点を欠いていました。ゆえに、オウムに対して研究者が行うべき仕事が果たされていない、中でも島田裕巳さんや中沢新一さんに対しては、本来宗教学者としてやるべき仕事をまったく行っていないと考えていたのです。
■中沢新一の著作は、ネタ本として教団内に転がっていた
――著書の中でも、中沢さんや島田さん、また宮台真司さんについては批判的ですが、学者が本来、オウム事件に関してやるべきこととは何でしょうか?
大田 まず第一に、善悪の価値判断に関わることや、個々人の生き方を左右するようなことを、軽々に発言するべきではないということです。私は中沢さんに対して極めて批判的ですが、彼は事件当時、方向性を見失ったオウム信者たちを今後は自分が引き受け、彼らに生き方の指針を示すといったことを発言した。また、社会学者の宮台真司さんは、『終わりなき日常を生きろ』(筑摩書房)という著作を発表し、麻原の打ち出した方向性は間違っていた、ゆえに今後の主体はこうあるべきだというヴィジョンを、あたかも「新たなグルの指令」のような仕方で発信した。研究者という立場にありながら、「次は俺がお前たちの生き方を示す」といったメッセージを軽薄に発してしまったことには、大きな問題があったと思います。むしろ研究者は、安易に状況に介入するのではなく、その事件や現象がどのような歴史的経緯とメカニズムの上に成り立っているのか、あるいは、それが社会的に蓄積されてきたどのような問題によって生み出されたのかを、可能な限り客観的に説明することに努めるべきであると思います。
――中沢新一さんの『虹の階梯』(平河出版社)はオウム真理教のネタ本であると言われていますが、実際、オウムの教団内では読まれていたのでしょうか?
野田 教団の中では麻原の書籍以外は読んではいけないのですが、『虹の階梯』だけは転がっていましたね。
――麻原が『虹の階梯』について直接言及したことはあったのですか?
野田 それはありませんでしたが、教団の中ではネタ本として半ば公になっていたので、みんな参照はしていました。
大田 ポアという言葉をオウムに教えたのは、『虹の階梯』ですからね。
――ネタ本を書いて、その後、オウムに関する論考を発表していた中沢新一さんの学者としての態度についてはどう思われますか?
大田 宗教学者として、近代における宗教の在り方や問題をどのように捉えるかという、学問的フレームワークを持っているべきだったと思います。しかし中沢さんの経歴を見てみると、そういった学問的フレームワークを十分に時間をかけて習得したという形跡がどこにも見当たらない。研究者としてのアイデンティティーに思い悩んだままネパールに渡り、チベット密教の修行のノウハウを身に付けて日本に帰ってきた。そしてニューアカ・ブーム(1980年代に日本の人文社会系で起こった流行)の一躍を担う人物として、広く世間から受け入れられた。こうして、一研究者としてのエートスや倫理観であるとか、学問的ディシプリンをどの段階でも身に付けることなく、ニューアカ・ブームに引きずられるように「売れっ子知識人」になってしまったのだと思います。
――本書の中で書かれていますが、そうしたことが、中沢さんがオウム事件を総括していない理由なのでしょうか。
大田 私から見ると、中沢さんは、オウム事件を総括しようにも、そもそも「できない」のではないかと思います。中沢さんはニューアカ・ブームの波に乗って著名な知識人となり、その影響力から、非常に無自覚な仕方でオウムの運動を後押ししてしまったわけですが、そうした経緯全体を客観的に分析するための学問的フレームワークを、彼は持っていないのですから。ゆえにいつまでも、メディアからの言外の欲求に応じるような仕方で発言してしまう。そして学者という立場にありながら、その場その場の状況に流され続けてしまう。
野田 先ほど、宮台さんについても触れました。宮台さんは、ハルマゲドンを待ち望む「男の子的終末観」に対して、ブルセラ女子のように生きることが解決策だ、みたいなことを言っていましたね。
 大田俊寛氏。
大田俊寛氏。大田 宮台さんはオウム的な終末論に対して、自分が生きる意味を考えたり、歴史に目的を求めたりするような主体はもう古いと訴えました。そして、自分の体を売りたいときに売ってお金を稼ぎ、欲望を叶えていくような、意味に囚われない主体というものをブルセラ少女に仮託し、こうした新しい世代によって「まったり革命」が起こると唱えた。本書の中でも指摘しましたが、こうした発想のベースにあるのは、ポストモダン的なニーチェ主義です。目的なき永劫回帰の流れに身を任せ、意味に縛られていた畜群的主体性を脱却して、超人という新しい主体として生まれ変わるという、ニーチェ主義の焼き直しであると思います。中沢さんや宮台さんの言説の背景にあるポストモダン的なニーチェ主義は、思想史的に見ればまさにオウムと同根であるということを誰かが指摘するべきでしたが、そのような人物は当時どこにもいませんでした。
――話は戻りますが、大田さんはご著書と野田さんの本には共通性があるとおっしゃっていましたが、野田さんはどう解釈されますか?
野田 私は、死の問題について、『革命か戦争か』でもっと触れたかったのですが、どう考えていいか迷っている部分がありました。そして大田さんの本から、死の問題に関するヒントを得られたと思います。中世以前のキリスト教が支配している社会では、国家を含めたひとつのシステムの中で、死の位置づけが与えられていた。死を含めた、人生の意義づけが成立していた。しかし近代においては、宗教と死の問題が私的領域に追い込まれ、オウムのような宗教が出てきてしまった。近代の社会では、死というものを公の領域から遠ざけている一方、それに対して統一的な見解を見つけ出したいという欲望を反動的に掻き立てたところが、オウムにはあったのではないか。もちろん、中世のキリスト教社会での死の取り扱いが真実かどうかは別問題として、ひとつの基準があった。その基準がないというのは、近代におけるひとつの問題だと思います。
大田 死の問題についてですが、人間とは死者からいろいろなものを継承して生きている存在であるし、それによって社会を成り立たせている存在です。我々が話している言語だって、いま生きている人たちがすべて自分たちで創り上げたものかといえば、決してそうではない。我々より前に生きていた人たちが使っていたものを継承するという形で、言語を使い、生活して、社会を成り立たせているわけです。このように、死者との関係がどのようなものであるかということが、社会を成立させていく上で常に重要な事柄なのです。もちろん物理的に言えば、死者はもうこの世には存在しないので、死後の世界がどういうものか、死者の魂はどうなっているのかということは、宗教学の立場から赤裸々に言ってしまえば、どんなお話を作ってもその真実性を証明することはできないし、あくまでひとつの「フィクション」でしかないのですが。
――現代では死の問題は、非常にタブー視されているというか、なかなか触れづらい問題ではありますね。
大田 しかし、奇妙なことではあるのですが、死者に関するフィクションを創設し、そのフィクションを中心に据えておかないと、人間の社会はアノミー的状況に晒されてしまう。人類は、歴史が分かる限りでは、もう何万年にもわたって、死者に関するフィクション──それはすなわち「宗教」と言っても良いかもしれませんが──を中心に、社会や歴史を作ってきたわけです。しかし、ヨーロッパというある特定の地域で宗教戦争が数多く起こってしまったために、宗教的な事柄をめぐって争うのはもう止めよう、宗教を社会の中心に据えるのは止めにしようという合意が成立した。これは歴史的に見ると、大変例外的な状態です。そしてそこから、政教分離という非常に特異な社会形成の様式が編み出され、それによって近代という時代が作られたのです。
――日本も近代化において、政教分離原則を受け入れていますよね。
大田 私は、日本という国家は、近代という仕組みに「過剰適応」してしまったところがあるのではないかと思うのです。欧米では、さまざまな意見や議論があるにせよ、死に関わる問題は最終的にはキリスト教が担うのだという暗黙の了解がある。ところが日本では、近代が成立した歴史的経緯が捨象され、その表面的原理に過剰に適応してしまったところがある。そして、死とは何かという問題については、個々別々に勝手に考えてくださいという状況になってしまった。そこから、麻原が抱いたようなある種の幻想、社会ではとても共有できないような幻想が力を持つという状況が生まれてしまったのではないかと思います。
(構成=本多カツヒロ/後編に続く)
●のだ・なるひと
1966年生まれ。1987年東京大学物理学科在学中にオウム真理教に入信・出家。95年教団内で正悟師の地位に就く。以降、幹部として教団運営において指導的役割を果たす。2007年アーレフ代表に就任。09年3月「麻原を処刑せよ」と主張したことによりアーレフから除名。現在はNPO「みどりの家族」を立ち上げ、ホームレスの自立支援や脱会信者の支援に力を注ぐ。独自にオウム事件被害者の賠償問題にも取り組んでいる。
●おおた・としひろ
1974年生まれ。専攻は宗教学。一橋大学社会学部卒業。東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻宗教学宗教史学専門分野博士課程修了。博士(文学)。現在、埼玉大学非常勤講師。著書に『グノーシス主義の思想――<父>というフィクション』(春秋社)がある。
外からの視点。
中からの視点。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事