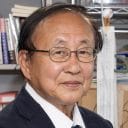原発依存症に陥った福島を生んだのは「中央への服従心」だった!?
#本 #インタビュー #原発 #東日本大震災 #東電
未曽有の大震災から早くも5カ月近くが過ぎた。ここに来て、首都圏の人々の注目は、津波による被災地よりも福島原発に多くが向けられていると言っていいだろう。自治体独自に放射線量を測ったり、個人でガイガーカウンターを購入し、家の周辺を測ったり、また脱原発デモを行ったりと。
しかし、そもそもなぜ福島県に原発が作られ、周辺住民がどう感じて生きてきたのかということを知らない「都会の人間」は多いのではないか? 福島県いわき市出身の社会学者・開沼博氏は、震災前の2006年から福島原発に興味を抱き、フィールドワークを重ね、内側から原発問題を考察してきた。その集大成が『「フクシマ論」 原子力ムラはなぜ生まれたのか』(青土社)である。今回、福島と原発の関係、そして震災後の世間の動きについて開沼氏に話を聞いた。
――そもそも福島原発に興味を持ったのはなぜですか?
開沼博氏(以下、開沼) 最初は2006年の夏前くらいに青森県・六ヶ所村核燃料再処理施設に行ったんです。行く前は「今でも根強く施設立地の反対運動が行われ、施設に嫌悪感を抱きながら声をひそめて生活しているじゃないか」というありがちなイメージを持っていた。しかし、実際にそこに住んでいる人に話を聞いてみると「原燃さん(六ヶ所村核燃料再処理施設の事業者)が来てくれたお陰で生活ができている」「1年の内の半分は出稼ぎに出ないといけない土地だったが、施設が来てから1年中家族と一緒にいれるようになった」と言う。福島に行ってみても、特に原発のある4町(双葉町、大熊町、楢葉町、富岡町)では「東京電力(以下、東電)が来てくれたお陰で」という雰囲気がある。そして、それは今も大きくは変わりません。そういう原発を抱える現地のことは東京から見ていたらわかりづらいことであって、その実態に興味を抱き調査をはじめました。
――開沼さんは福島県いわき市出身ですが、いわき市ではそういう雰囲気は感じられませんでしたか?
開沼 いわき市民が普段、原発を意識することはそれほどなかったですね。原発のある4町の人々も原発があることは知っているけれども、毎日「原発あるなー、怖いなー」と意識するかと言えば、そんなことはなかった。それは東京の人が「東京タワーがあることは知っているけれども、別に改めて昇ることはない」という感覚に近いのかもしれない。福島の4町には40年間にわたって原発があるわけですから、多くの人にとって「生まれた時から記憶の中に自然とある風景」なんです。
――本書のテーマは「日本の戦後成長と地方」ですが、このテーマに興味を抱いたのは?
開沼 そもそもの学術的な話で言うと、「成長社会が終わったあとは、どういった社会になるのだろう」ということを考えたかった。「ポスト成長社会」と私は呼んでいますが、これまでもそれを「成熟社会」とか「縮小社会」と名づけて捉えようとしたり、もちろん「成長はまだ終わっていないんだ、そうするためにがんばるんだ」という立場もある。でも、こんなことになってしまったのも含めて、どうすればいいのか考えあぐねているのが実情だと思います。このテーマについて、もうひとつ抽象度を上げると「近代」がテーマになります。社会学は「近代社会とは何か」を問う学問だと私は思っています。しかし、その近代社会が曖昧になりつつある。成長が終わるとは、そういうことかもしれないなと。じゃあ今までの理論で捉えられない近代を、どういう視座から捉えていくことが必要なのかと考えたのが、最初の問題意識でした。そこで考えたのが、戦後の成長を、私が理論的な下敷きとしたポストコロニアリズム(ポスト植民地主義)との関係で捉えていくという方法でした。日本の中央と地方との関係にある種の「植民地性」を見ることで新たな社会の描き方ができるのではないかと思ったんです。
■地元民には、東電に対する「信心」がある
――福島県は只見川電源開発、常磐・郡山の新産業都市などを誘致しています。かつて貧しかった一帯が地域振興策の中で一番魅了的な原発を誘致したのは、貧困を克服するためというのが一番大きかったのでしょうか?
開沼 原発のある地域が取り立てて貧困だったかというと必ずしもそうではないんです。1950年代、60年代の日本はまだ道路もコンクリートになる途中の「途上国」です。映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の世界ですね。その場その場に合った地域開発が日本のあらゆるところで行われていました。たまたま福島県の沿岸地域では、すべての市町村に発電所を置いていくような開発が行われた。発電所は大量の雇用を生みますし、地域開発としては有効でした。そういう流れの中で、たまたま原発が置かれたというのが私の認識です。
――仮に原子力でなくても良かったということですか?
開沼 原子力でなくても良かったと思います。それが巨大公共事業とか工場などであっても良かったと思います。だから、用地と海水の確保などの条件さえ整えば、どの地域でも福島になる可能性はありました。
――テレビで見る成長著しい東京と地方ではかなり違ったのでしょうか?
開沼 その当時、日本は豊かであるという幻想ができ始めていました。それはメディアを通して作られていた。ベネディクト・アンダーソンの言葉でいう「想像の共同体」ですね。テレビでは東京オリンピックや『ひょっこりひょうたん島』が流れるのを見ながら、自分たちの想像の中では、日本という国は非常に豊かで、イケイケドンドンであるというイメージがある。にもかかわらず、いざテレビを消して、家の外を眺めてみると、とんでもないクソ田舎であると。当然都会になりたいという欲望が生まれる。そこでスッと差し出されたものが原子力であったんだと思います。
――本書の中で、そうしたムラと国・中央がaddictional(常用的に、依存的に)な関係になってしまうと指摘されています。addictionalな関係とは具体的にどういうことでしょうか?
開沼 ムラが原発をどんどん欲していくような中毒的な状況を指します。経済的な話が一番わかりやすい。原発は一回置くと、最初はかなりのお金が入るんです。ですが、固定資産税からの税収は年々下がり、一方で金がある時に作った施設のメンテナンス費はかさむ。時間が経つとともに財政的に厳しくなっていきます。減った収入分を埋め合わせるために原発なり関連施設なりをさらに建設してくれということになってしまいます。
――他の観点だと?

開沼 本書の中でも触れていますが、一番肝になるのは文化的にもaddictionalになってしまうことです。たとえば、「原子力モナカ」というお土産物が売られていたり、国道沿いに「回転寿しアトム」という寿司屋があったり。東京の人から見れば特異な光景かもしれませんが、地元の人にとっては大きな違和感もなくそれが存在している。それだけ「原子力ブランド」が浸透し、原発と共生する社会が確立していると言える。
――そうした地域に、原発によって経済的な恩恵を受けている人はどれくらいいるんですか?
開沼 いろんな捉え方がありますが、人口の3分の1から4分の1は原発関連で生計を立てていると思います。その家の人が原発関連で働いていなくても、親戚付き合いや近所付き合いはあるので、なんらかのステークホルダーになってしまう。そう簡単に「原発は危ないから嫌だ」と言える状況ではないんです。原発関連で働くと言っても、今メディアで報じられるように白い服を着てマスクをつけている人だけではなくて、実際にはガードマンの仕事があれば、瓦礫をトラックで運び出す仕事や仕出しの弁当を作る人、原発の中で働く人を相手にした保険外交員もいる。年配の人や技術がない人も含めて原発ではたくさんの人が働いている。
――ムラと中央がaddictionalな関係になると、ムラが中央に「自動的かつ自発的に服従」するような関係が生まれると分析されていますが?

開沼 それは何段階かに分けて分析しています。最初の段階では、どうにか自分たちの田舎を都会に近づけるために、他の地域と競い合いながら新幹線や高速道路を持ってくるみたいな形で、中央に対して「自発的な服従」をしていくようになった。それがいつの間にか財政的な問題や文化的な問題でaddictionalになっていき、「自動的かつ自発的な服従」が完成したという風に私は捉えています。ここでのポイントは「服従」が、その言葉から想像しやすいような権力による強引な支配によるどころか、むしろ、服従する側が勝手に権力にひれ伏してしまうという一見奇妙な現象が起こっているということです。
――こうしたムラと国の服従の関係は日本の他の地域でもみられますか?
開沼 一番理解しやすい例が、財政破綻した夕張市です。かつて賑い日本中に名が通った街が、巨大資本の撤退とともに一気に寂れる。地域と国との間にある種の共依存関係ができている。同じようなことはどこでも起こりえます。
――そうした服従の中で東電信仰のようなものが果たした役割は?
開沼 それを本書の中では「信心」と呼びました。2000年代の初めに東電で事故や隠蔽事件がありましたが、ある町長さんは「東電を信じて共に歩んでいくことが私たちにとっていいことなんです。それしかありません」と発言している。そして、地元の人も「東電が大丈夫だと言っているから、大丈夫でしょう」と納得してしまっていた。それ故に3.11間際まで原発は維持され続けた。
――もし福島に原発がなかったら、福島はどうなっていたと思いますか?
開沼 財政状況は現状以上に悪かったでしょう。ただ、原発がなくてもやっていける自治体は他にいくらでもありますから、なにか困ることがあったかというとそれはわからないです。しかし、歴史を振り返れば「原発なき福島」を想像すること自体困難だとも言えます。本書の中でも検討しましたが、明治以来、福島は東京から「ほどよい位置」にあった。明治の初期から水力発電で東京の蒲田まで電気を送ったり、戦中は、石川町でウラン鉱石を採って、日本の原爆開発計画に貢献した。戦後すぐ、只見川電源開発や、映画『フラガール』でも有名になった常磐炭田のように「エネルギーの供給地」として東京の成長を助けていた。東京の成長を常にサポートする役割を日本の近代化の中で福島は担わされてきたんです。
■デモが起きても「フクシマ」は忘れられる運命!?
――ここからは3.11以降のお話を中心に聞きたいのですが。まず、4月10日には高円寺で脱原発デモが行われ、1万5,000人の人が集まりました。これに対して本書の中では批判的に言及しています。
開沼 いや、やってる方がいるのは全然いいんです。でも私自身は参加する気はない。震災前から労働組合のある党派は、40年間原発反対運動をしてきたわけですね。それが有効な手段ではなかったから原発はなくなっていない。答えは、もう出ています。1万5,000人は確かにすごいと思います。いわゆる「生きづらい若者」にとっては「居場所」として非常に意味があったとは思いますが、脱原発という点では無効だと言わざるを得ない。そして、ただ無効なだけなら放っておけばいいですが、デモ自体がハラスメントにつながりかねないことに無自覚なままになされている故に批判をせざるをえない。「即座に原発をなくせ」ということが、ただでさえ生活が苦しい原発立地地域の人間にとっては仕事を奪われることになる。それがどれだけウザいか。「奇形児を作らせるな」と障がいがある方もデモに参加している中で叫ぶ。新たな抑圧が生まれかねない状況がある以上、手放しでは見過ごせません。
――1年前、沖縄米軍基地問題では人々はあんなに熱狂していた。にもかかわらず今では誰もそんなことを気にしないままに粛々と問題の処理が進められている、という例を出されていましたが、福島原発もいずれ忘れ去られてしまうのでしょうか?
開沼 それは間違いありません。東電なり経済産業省なり文部科学省の原子力政策を担う部門は、とりあえず福島の原発から放射能物質が出ないように押さえ込みさえすれば、この問題は解決すると思っている。押さえ込んでしまえば、今原発に関心を持つ人も、少なからず、元通りの無関心派になります
――自分たちの生活に直接危害がなくなると関係がなくなってしまう?
開沼 原子力ムラの当事者ではない人の関心は2点に収斂されます。結局、この復旧作業の落とし所はどこなのかということと、出ちゃっている放射能はどんだけ危険なのかということです。その答えがわからないから、イライラしてデモに行ったり、ガイガーカウンターを買って計測したりしている。逆に、その答えがある程度明らかになれば、そこに「日常」が戻ってこざるをえない。もはや原発に関心を持つ理由はなくなっていく。言い方を変えれば、デモを今の規模で続けるためには福島に不幸であり続けてもらう必要がある。これはある面で事実です。「イライラ」をガソリンにして「脱原発」のエンジンを回している。その裏にある「ありものの知識や知識人への信頼の仮託」の構造は、3.11の前も後も何も変わっていません。そして、それは時間の経過の後に形は違えど同じ問題を反復することにつながります。そこから逃れるためには、シンプルに言えば、歴史を見ることであり、東京からは見えにくい現場のリアリティに向き合うことなんじゃないかと思います。
――いわゆる知識人の発言が右往左往している印象もありますが。
開沼 勝手に右往左往するだけならいい。ただ、必死に逃げてよくわからない言い訳をしたり、よくわからないにもかかわらず、とりあえずヒステリックに脱原発派を煽ったりすることは混乱を増長させるだけ。知らないなら知らないでいい。怖いなら怖いでいい。あとは黙ってればいい。今回の原発を受けての知識人たちの行動、インテリと呼ばれる層にいる人間たちの短絡的な行動が、結果的に一般の人たちの不安をますます煽っているだけなのだとすれば残念です。
――そういう中で自然エネルギーの話も出ていますが。
開沼 自然エネルギーは悪いと思いません。また、原発の是非の立場を問われた時に「長期的には脱原発に向かうのがいいと思う立場です」と答えておくのが現状のベストアンサーです。どっから弾が飛んできても怪我をしません。でも、少なくとも原発周辺に住む人々にとっては、今食っていけるか否かが重要。今、あるいはこの先に自分たちの生活を支えるものでないなら、どうでもいい。「外野からどうこう語る知識人」ほどの理想主義的な幻想は持っていない。現実を見ている。当然のことです。そして、もとから原発で働いていた人にとっては、得体の知れない幻想に乗り換えろと騒ぎ立てられるより、淡々と原発を動かしてほしいというのがとりあえずの本音。「自然エネルギーを導入すれば新たに雇用が生まれる『はず』です」と言う「善意」ある言葉を投げかけた時に「そんな不確定のことのために人生をかけられません」「それまでどうやって食っていけばいいんですか、生活費あなたが払ってくれるんですか」という問いは当然返ってくる。
――今後、原発について考えていかなければならないことは何でしょうか?
開沼 まず第一に、成長のために地方を踏み台にしてきたことを認識しなければなりません。本書の中で「2つの原子力ムラモデル」を提示しました。つまり一方には、電力会社や政府を中心とした「原発を置きたい側」=中央のムラ、もう一つは、「原発を置かれたい側」=地方の側の原子力ムラがある。政府叩き・東電叩きをしてカタルシスを得ることに終始するのは無意味。この、私たちが無意識のうちに踏み台にしてきた「2つの原子力ムラ」を変えて行く必要があることを認識しなければなりません。
――最後にこの本をどんな人に読んでほしいか。また、まだ読んでいない人へ一言お願いします。
開沼 何か原発について声を大にして主張したがる人に読んでいただければと思います。主張するなと言っているのではありません。その気持ちが圧倒的な「善意」に基づくという自覚があったとしても、実は知らぬ間に暴力や抑圧に転化してしまっていることを受け止めなければならない。一言で言うならば、「まず原子力ムラを肯定せよ」ということです。私たちは、原子力ムラの上に乗っかってきたし、黙認しながら生活をしてきた。必死に何かを叩きのめしたい気持ちはよくわかります。ただ、間違いなく、その叩きのめしたいものは、昨日の自分自身の顔そのものです。これまでは改めて鏡に映して意識することはなかったかもしれないけれども、事実としてこういう顔をしていたんだということをまず受け止めなければならない。日本の近代、あるいは戦後成長が無意識的に乗っかってきた基盤がそこにある。不安・不満解消のためのセンセーショナルな反応はすでに一巡しつつある。その先にあるのは愚かな反復でしかない。原子力ムラを一度受け入れる、つまり、それによって成り立ってきた「原発がある幸せ」を無意識的にせよ選択してきてしまっていた、今もいる、ということを改めて捉えなおす必要がある。その後に初めて「原発なき幸せ」についての議論が始められます。
* * *
福島原発関連の本は数多く出版されているが、内側から迫った本は少ないのではないだろうか。福島原発に対する新たな視点を与えてくれることは間違いない。
(文=本多カツヒロ)
●かいぬま・ひろし
1984年福島県いわき市生まれ。2009年東京大学文学部卒。2011年東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。現在、同博士課程在籍。専攻は社会学。
なぜ?
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事