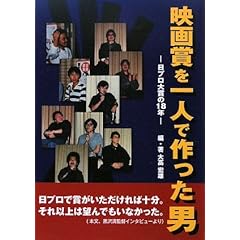“ゼロ年代映画”ベスト作品はどれ? 邦画活況がもたらした10年を検証
#映画 #インタビュー
 映画ジャーナリスト・大高宏雄氏が「ゼロ年代を代表する傑作」と評する三池崇史監督、
映画ジャーナリスト・大高宏雄氏が「ゼロ年代を代表する傑作」と評する三池崇史監督、浅野忠信主演『殺し屋1』。映像表現の臨界点に達したバイオレンス映画だ。
(C)山本英夫/小学館「殺し屋1」製作委員会2001
時代を映す鏡である映画は、2000年代の日本社会をどのように活写したのか? 『日本映画のヒット力』(ランダムハウス講談社)などの著書を上梓している映画ジャーナリストの大高宏雄氏は、18年の歴史を持つ「日本映画プロフェッショナル大賞」(略称、日プロ大賞)の主宰者としても知られる。日プロ大賞とは興行的に恵まれず、メジャーな映画賞からもスルーされたものの、評価すべき作品や監督、俳優たちを顕彰し続けている独立系の映画賞だ。邦画冬の時代から日プロ大賞を自腹で主宰してきた大高氏は、多様化した日本映画のこの10年をどう見ているのか。”ゼロ年代”を代表する日本映画ベスト5を挙げてもらいつつ、日本映画界の現状、そして今後について語ってもらった。
●大高宏雄氏が選んだ”ゼロ年代”日本映画ベスト5
1.三池崇史監督『殺し屋1』(01)
2.万田邦敏監督『UNloved』(02)
3.黒沢清監督『アカルイミライ』(03)
4.山下敦弘監督『リアリズムの宿』(04)
5.松本人志監督『大日本人』(07)
──ゼロ年代を代表する日本映画を5本挙げていただいたわけですが、『大日本人』以外は日プロ大賞でおなじみの監督たちのインディペンデント系作品が並びましたね。
大高 ゼロ年代を代表する監督となると、やはり三池監督、万田監督、黒沢監督、山下監督は外せないでしょう。それに『ユリイカ』(01)、『サッド ヴァケイション』(07)の青山真治監督を加えてもいいかもしれません。中でも三池監督は90年代から走り続け、その表現スタイルがゼロ年代に入って開花した印象がありますね。『殺し屋1』は、間違いなく三池監督の数多い作品群の中でひとつのピークに達した作品と言えます。バイオレンスを扱った内容のため、女性客や映画賞からは無視された作品ですが、コミックを原作にしている点でもゼロ年代的ですし、エンターテイメント映画として表現の限界を極めた作品として特筆されるべきでしょう。
──松本人志の監督デビュー作を挙げている点が、異色であり、また大高氏らしいセレクションです。
大高 2作目となった『しんぼる』(09)はひとりよがりに走り過ぎた感があり残念でしたが、『大日本人』は一般的なマーケティングや企画開発、プロデューサー的な発想などを全て取っ払ったなか、個人的なレベルで何が映画でできるのかを問うた作品として、とくに挙げたいですね。
このデビュー作において、松本人志は自分の思い通りのことをやってしまったわけです。これは今、なかなかできることではありませんし、面白いんですよ。世界そのものをバカバカしさで塗り込んでやろうという、彼の欲望とその実現は、今のこの時代に有効性があると感じます。その熱情は、あきれ果てるほどでしたが、やり方があまりに突拍子なため、その特異な世界に入れる人、入れない人の両極端を生んでしまうわけです。一種の個人映画と言ってしまってもいいですね。
ゼロ年代を振り返った際、人間社会における”個”の存在というものをどう捉えているかという重要なテーマがあるのではないでしょうか。だから、”個”と”個”の距離感を描いた映画に秀作が多く生まれているのも見逃せませんね。
万田監督『UNloved』は男と女の距離感を新しい視点で描いたものだし、黒沢監督の『アカルイミライ』は浅野忠信とオダギリジョー演じる兄弟分の共生観を描き、山下監督の『リアリズムの宿』はつげ義春が60年代に発表した漫画の中の旅人と旅先の人や風景との距離感を現代的に捉え直した作品。ゼロ年代映画のキーワードとして、”個”と”個”の関係性をどう描くのかという重要なテーマがある一方で、”個”の爆発そのものを描いたのが『大日本人』だと考えることができると思います。
──便宜上5作品を選んでもらいましたが、その他にも注目するべき作品は多いかと思います。
大高 次点としては、高橋洋監督の『ソドムの市』(04)を挙げたいですね。サブカルという言葉はすでに死語でしょうが、この作品はサブカルのその先を行ってしまったような作品。というより、そうした言い回しさえ、超えてしまっているような別次元の作品ですよ。まあ、何とも表現のしようがありません。批評がほとんどなかったのは、この作品が批評そのものを拒否しているからでしょうね。大好きな作品です。
ドキュメンタリーから1本挙げるなら、中村高寛監督の『ヨコハマメリー』(06)。『ヨコハマメリー』といい、09年に公開された松江哲明監督の『あんにょん由美香』といい、問題提議的なこれまでのドキュメンタリーとは違う新しい流れが生まれている。何らかの問題意識を訴えることよりも、被写体をカメラが素直に追っていく過程にいくつかの仕掛けを施しながら、最後には「えっ?」と驚く展開を用意し、とにかく見ていて固苦しくなく、面白ささえ感じさせてしまう。ドキュメンタリーの作り方がゼロ年代に入って大きく変わっていることを痛感します。
また、ゼロ年代の後半から『ゆれる』(06)の西川美和監督、『ウルトラミラクルラブストーリー』(09)の横浜聡子監督ら女性監督が注目される存在になってきた。荻上直子監督の『かもめ食堂』(06)も、すごくゼロ年代的な作品。もう”女性”監督と呼ぶこと自体はばかられるわけですが、彼女たちが今後新しい流れをどう作るのか期待したいところです。
──今回挙げられたインディペンデント系の監督たちの中から、メジャーシーンに風穴を開けるような人物は出てくるでしょうか?
大高 時代劇『十三人の刺客』が公開待機中の三池監督は、90年代はVシネで娯楽作品を量産し、2000年代に入って、その技量を一段と開花させ、今はメジャーシーンでの新しい段階に移行しつつあるところでしょう。でも、先に挙げた映画監督たちは基本的にそういった方面での野心を持っていないように感じますね。実際に、そうなのかはわかりませんが。メジャー指向を感じさせないのは、日本の映画監督たちのナイーブさと関係あるかもしれません。ちょっと物足りないとろでもありますけどね。『母なる証明』(09)を撮った韓国のポン・ジュノ監督などとは違いますね。
『トウキョウソナタ』(08)を撮った黒沢監督も、今すぐメジャーで映画を撮ることを望んでいるようには見えない。でも、黒沢監督は東宝配給で『スウィートホーム』(89)というエンターテイメント作品を過去に撮っています。また違った形でメジャー映画を撮ってみても面白いはず。
万田監督は東映配給で『ありがとう』(06)を撮っていますが、こうした大作にもさらに挑戦してほしいですね。この作品は、阪神大震災を再現したシーンにお金が掛かり、製作費の回収が難しかったと聞きます。万田監督を起用したのは、仙頭武則氏ですが、本作の収支が厳しかったのか、今は製作ができる状態ではない。98年に松竹を解任された奥山和由氏もそうですが、監督と協調し合って映画製作できるプロデューサーの存在は重要。実力のある監督たちを単館系の中に押し込めるのではなく、うまくメジャーの中で活かすプロデューサーが必要です。そうでないと、今のようにテレビ局主導で、テレビディレクターが監督まで手掛ける映画ばかりになってしまいます。
キャリアの充実期にある監督たちがプロデューサーと企画やキャスティングを一緒に練りながら、ある程度予算の組まれた映画を作っていくことが2010年以降は求められるでしょうし、そうなって欲しいと思いますね。
──ゼロ年代最後の2009年を振り返るとどうでしょうか? 「キネマ旬報」11月上旬号の”ファイト・シネクラブ”でテレビ局参入によるマーケティング至上主義の弊害を唱えた大高氏の記事はとても印象に残っています。
大高 ボクはテレビ局が参入したことで、映画館に観客が戻ってきたことを評価しています。映画興行を成立させることが、何と言っても大事ですから、マーケティングを重視した映画があってもいいし、当然のことです。ただ、この1~2年で市場原理主義というようなマーケティング主導の映画製作が、ちょっと度を超してきた気がしてなりません。あまりに人気獲りだけを考えた映画ばかりを連発していると、また邦画は飽きられて冬の時代に戻ってしまう。これを危惧します。ときには通り一辺のマーケティングを無視したような無謀とも言える野心的映画も必要。09年に公開された若松節朗監督の『沈まぬ太陽』は演出に不満があるものの、テレビ局に頼らずに映画会社の意地を見せた企画として木村大作監督の『劔岳 点の記』と並んで評価しています。
──三部作『20世紀少年』の最終章『ぼくらの旗』のラスト10分が試写では伏せられたまま公開されたことも業界内で波紋を呼びました。
大高 映画ジャーナリズムが軽視されているということですよ。作品が評論されることよりも、ネットに情報が流れてネタばれされる危険性を恐れられた。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』も、公開前にネットでネタバレが出て、すったもんだした。背景に、映画ジャーナリズムの軽視があると思います。が、一方ではプロの評論家ではない、一般ブロガーを優先した試写も催されるようになってきており、配給会社はその中身を結構気にするようになっています。
また、今回挙げたインディペンデント系作品とは別に、85億円の興収を稼ぎ、観客満足度90%超(ぴあ調査)の『ROOKIES 卒業』を映画評論の立場からどう見るかという問題もある。”こんなの映画じゃない”と批判しても、それは不毛なこと。一体その批判をして、そのことを誰に伝えたいのか? 『ROOKIES』に満足した人たちは、そういった批評は読みませんよ。いくら批判記事を書いても、それは自己満足に過ぎないわけです。映画批判に関しては、新たな批評の形が必要な気がしますね。今、映画評論が置かれている意味、映画と活字の関係についての問題は、また改めて考えるべき深いテーマでしょう。
 2009年11月に『映画賞を一人で作った男 日プロ
2009年11月に『映画賞を一人で作った男 日プロ大賞の18年』(愛育社)を出版した大高宏雄氏。
「3~4月には日プロ大賞の授賞式を考えています。
お客さんに楽しんでもらえるようなイベントにしたい
ですね」と語る。
──日プロ大賞は2002年から授賞式が途絶えていましたが、09年度は授賞式を開催するんでしょうか?
大高 3月か4月に、各賞受賞者を招いてのイベントを考えています。今回の受賞候補になりそうな作品は、園子温監督『愛のむきだし』、高橋玄監督『ポチの告白』、鈴木卓爾監督『私は猫ストーカー』、松江監督『あんにょん由美香』などでしょうか。それに加えて、作品賞にどこまで食い込むか注目されるのが細田守監督のヒット作『サマーウォーズ』。今までのアニメの流れとは違った新しさを細田監督は感じさせます。
日プロ大賞は単館系の作品を中心にこれまで選出してきましたが、単館系は単館拡大になり、さらに今ではシネコンの普及により、上映形態が混沌としてきました。単館系の意味が大きく変わり始めているわけです。メジャー系とインディペンデント系の区分もあいまいになっていますよね。”インディペンデント系”とひと言では括れなくなっている。そうした背景を含め、日プロ大賞も新しい方向性を打ち出していきたいと考えています。
* * *
メジャーな映画賞とは一線を画する日プロ大賞は、ゼロ年代最後の賞をどの作品に贈るのか。また、ゼロ年代映画に続く、新しい映画の流れは生まれつつあるのか。時代を映す鏡である映画の変貌をこれからも追っていきたい。
(取材・構成/長野辰次)
●おおたか・ひろお
1954年浜松生まれ。明治大学文学部仏文科卒業後、映画ジャーナリストとして現在にいたる。「キネマ旬報」で”大高宏雄のファイト・シネクラブ”を好評連載中。映画界の興行に精通し、『日本映画のヒット力 なぜ日本映画は儲かるようになったのか』(ランダムハウス講談社)などの著書がある。また、92年より毎年1回、「日本映画プロフェッショナル大賞」を主宰し、2009年11月には18年にわたる同映画賞の歴史をまとめた『映画賞を1人で作った男 日プロ大賞の18年』(愛育社)を上梓した。
日本映画の近代史そのもの。
【関連記事】 園子温『愛のむきだし』で満島ひかりが”むきだし状態”に!
【関連記事】 「同じことばっかりやってて、面白い?」細田守が”家族肯定”に挑んだ理由
【関連記事】 松本人志監督・主演第2作『しんぼる』 閉塞状況の中で踊り続ける男の悲喜劇
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事