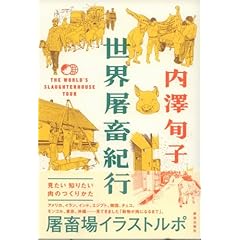屠畜は本当にタブーか? ルポライターが見た「真実」
日本のみならず、韓国、モンゴル、インド、アメリカなどで、国内メディアからはタブー視されてきた屠畜(屠殺)事情を取材したイラスト・ルポルタージュが、ノンフィクションとしてはヒットといえる2万5000部を発行して、話題になっている。タイトルは、『世界屠畜紀行』(解放出版社)。この骨太なテーマに挑んだのは、意外にも女性。現在、朝日新聞で連載小説のイラストを手がけるなど、売れっ子イラストルポライターの内澤旬子さんだ。では、なぜ屠畜取材を? さっそく本人を直撃してみると、いわゆる「知らなければならない、つらい現実に目を向ける」という姿勢ではなく、純粋に屠畜への関心が高かったのだという。
「たまたま旅行先のモンゴルで内臓の腑分けを見て、『解体を、もっとちゃんと見たい』と思ったのが直接のきっかけだったんですが、もともと子どもの頃から解剖が好きだったんですよ。高校時代も、文系クラスにいたのに、カエルの解剖の時だけ理系の授業に忍び込んで、嫌がる女子に代わって執刀したりして(笑)」
魚をさばいて、胃と腸がつながっているのを見て、生命の奥深さを実感し、感動する──内澤さんにとって、屠畜への興味はその延長線上にあったが、しかし、日本で、屠畜の現場に触れようとする中でタブーにぶち当たる。
「私自身は、神奈川の新興住宅地で生まれ育ったこともあって、屠畜という仕事を押し付けられてきた『部落』や『同和』などという言葉は大学に入るまで知りませんでした。ただ、取材される側の人には、そうした歴史的な背景に加えて、屠畜そのものに対する偏見の目にさらされてきた経緯もあって、最初はすごく緊張されましたね」
 東京都中央卸売市場食肉市場(通称「芝浦と場」)
東京都中央卸売市場食肉市場(通称「芝浦と場」)食肉産業の伝統を支えてきた被差別部落の人々に対する、不条理な職業差別の歴史。差別の意識が消えても残る、屠畜への無理解。89年に『ニュース23』でキャスターの筑紫哲也氏が、ある国際ニュースに際して「(麻薬の値段が上がったら)ニューヨークの街が屠殺場になる」と発言し、屠場労組や部落解放同盟から糾弾を受けたのはよく知られているが、メディアでは、無知ゆえにしばしば屠畜を残虐行為のように表現してきた過去がある。
「それに、屠場に取材にやって来た人が、動物が殺されるところを見てビビったり、においに顔をしかめたりしたら、やっぱり、現場の人は傷つきますよね。それで、『そういうものは、人に見せるもんじゃない』と、現実にふたをするようになる。でも、屠畜は高い技術がなければできないこと。外国では、あっけらかんとやっているところも多いですから、これまでとは別の見方を提示できないかな、という思いはありました」
内澤さんの「屠畜取材をしたい」という持ちかけに、多くのメディア関係者は抗議や糾弾を恐れて強力なアレルギー反応を示したというが、たまたま解放出版社に知り合いがいたことと、すでに世界の屠畜をルポしてきたという下地から、メディアの取材が難しいといわれる芝浦と場の内側に入ることを許される。取材は長期に及んだ。
「一番うれしかったのは、描いて喜ばれたことですよね、現場の人に。『この背中は俺だ』とか(笑)」
“眉をひそめられるのではないか”という懸念が吹き飛べば、職人技が駆使される自らの仕事を理解してほしい、という現場の思いも湧き上がる。そして、今、こうした思いを受け止める層が着実に増えているという。
「今、屠畜を含む、食の生産現場を取材したドキュメンタリー映画『いのちの食べかた』(ドイツ映画)がロングランヒットになっているんですが、観客の多くが30代以下の若い世代なんですね。屠畜に関してメディアが、 “黙して語らず”の時間があまりにも長かったため、彼らは『そういえば、(食肉加工の過程を)知らなかった』という感じで見に来ている。今から(タブー意識のある)年配層を啓蒙しても人の価値観はそう変わるもんじゃないですが、若い世代には、むしろ作業現場の情報をオープンにすることで、屠畜への偏見をなくすことはできるんじゃないかと思います」
これまでのタブーがタブーでなくなる日も、そう遠くないかもしれない。
(編集部/「サイゾー」4月号より)
肉を見る目が変わるかも?
内澤旬子
イラストルポライター。緻密な画風と旺盛な行動力で、世界各地を旅し、図書館、トイレ、製本などの現場も取材。著書に『センセイの書斎』(幻戯書房)など。
『世界屠畜紀行』
世界各国の屠畜現場へ自費取材を観光。韓国やインドなど、日本と同じく、屠畜に「差別意識」が残る地域の実態も緻密かつ温かみのあるイラストで詳細にレポートしている。(内澤旬子・著/解放出版社/税込2310円)
【もっと読む】 サイゾーおすすめ本
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事