
【小田嶋隆】世田谷区――実家に置いてきた娘に合わす顔がないある女の話
東京都23区――。この言葉を聞いた時、ある人はただの日常を、またある人は一種の羨望を感じるかもしれない。北区赤羽出身者はどうだろう? 稀代のコラムニストが送る、お後がよろしくない(かもしれない)、23区の小噺。
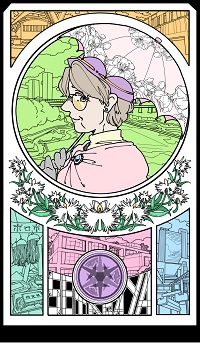 (絵/ジダオ)
(絵/ジダオ)「トロフィーワイフ」という言葉がある。功成り名遂げた男が、自らの人生の成功の証として手に入れる賞品のような妻、といったほどの意味だ。
駒沢競技場を望むオープンカフェで、談笑するマダムたちのいずれ劣らぬこれみよがしな美貌を眺めながら、静子は昔、なにかの本で読んだトロフィーワイフという言葉を思い浮かべている。万事にカネのかかった女たち。カネの出どころは本人ではない。アタマからつま先までを積算して合計すれば、100万円はくだらないはずのその彼女たちの服飾関連出費を鷹揚に支出しているのは、10歳以上は年齢が上の夫ということになっている。
日曜日の午後、駒沢公園前のカフェに集うマダムたちは、自分たちが買い取られた資産であり、自分の脚で歩く期間限定の不動産である旨を強く自覚している。だからこそ、個々のトロフィーワイフは、自身に投入された金額の多寡を、端数の10円の単位に至るまで頑強に記憶しているのだ。
その点、私は、身に着けているもののすべてを、一から十まで、自腹で買い揃えている。そういう意味で自分はトロフィーではない。
「どちらかといえば」
と、静子は考える。
「あたしはトラップなのかもしれない」
スマホが鳴る。通話の着信音ではない。LINEの通知を知らせる幽かな擦過音だ。その曇りガラスを引っ掻くような神経に触る音色を、彼女は、メッセージを伝える効果音に採用している。
「いま渋谷。あと30分でそっちに着くよ」
娘からLINEのメッセージが届くようになったのは、2カ月ほど前からのことだ。
それまで、静子は、彩美がスマホを持っていることさえ知らずに過ごしていた。今年の4月、福島の母親のもとにもう5年も預けっぱなしにしている彩美が、突然電話をかけてよこしたのは、中学に入学して、自分用のスマホを手に入れたからだった。
「おかあさん。あたし。わかる?」
彩美は屈託なく笑っている。まるで天使みたいに。5年も会っていないのに。小学2年生の夏休みに実家に置き去りにして、以来、ハガキ一枚、電話一本よこしていない母親を、このコは、まるで恨んでいないように見える。本当だろうか。
「ねえ。おかあさん。あたしのLINEに登録してよ」
以来、彩美は、週に1度か2度、近況を短い文章とスタンプで知らせてくるようになった。
「席替えがあったよ」
「隣の席のオトコ最悪。やくざものだよ」
「部活やめたよ。面白くないからね」
「ねえ、英語って必要? 誰に使うの?」
「カズが金髪にして呼び出しくらって金髪のボウズになって、で、3日で色がぬけた。超ウケる」
静子は、メッセージを受け取る度に、5文字以内の簡単な返事を書く。文字の入力が得意でないということもあるが、本当のところ、どんなふうに返事をして良いのやら、毎回見当がつかないのだ。
「あら」
「おやおや」
「素敵」
「なるほど」
静子は、内容にかかわらず、その都度適当な相槌を送る。そういえば、一緒に暮らしていた頃、健二に言われたことがあった。
「お前の返事には心がこもっていない」
もっとも、その時に健二が指摘したのは、静子の生返事のことだった。確かに、健二の話を聴く時、彼女はどうかすると
「ふん」
という、どことなくバカにしているように響く短い相槌を返していたものだった。
「その、ふん、ってのをやめろよ」
と言われた時、静子ははっきりした声で
「ふん!」
と言った。いつもの、鼻息ひとつの「ふん」とは少し違う気持ちをこめたつもりだったが、健二にはうまく伝わらなかった。
「おまえは本当に手に負えない女だな」
そう言って健二は真面目な顔で彼女を見た。
そうするのは、機嫌の良い時の健二の癖だった。その健二もいまはどこにいるのかわからない。
「まあ」
「!」
「そうね」
「知ってる」
「素敵ね」
静子は送信する。その静子の短い返信を、彩美はおおげさに面白がる。
「『素敵ね』ってリプ、ちょーウケる。最高だよね。昭和のリッチなマダムみたい。あたしも使わせてもらう。すっごい素敵だよ」
渋谷に着いたという彩美からの短信を受け取って10分ほどが経過した頃、静子は、突然、自分が、この場に似つかわしくない身なりをしていることに思い当たった。この店のあちこちに座っている小型犬を連れたマダムたちの、一点のスキの無いいでたちと比べて、自分の髪と服装の、なんとみすぼらしく映ることだろう。そう、彼女は思った。もちろん、普段ならそんなことは気にしない。私は私だ。自分の髪の色と大きなトートバッグと常に我が身と共にあるトップスとボトムスを、私は自前の経済力で買い整え、持って生まれたオリジナルの感覚でコーディネートしている。誰に対して何を恥じ入ることもないし、みじめに感じる必要もない。今、羽織っているワインレッドの革製のハーフコートは、もう4年も着ている韓国製のフェイクだが、モノ自体は悪くない。靴もピアスも特段の高級品ではないが、出自を恥じねばならないような安物でもない。
「でも」
静子は考える。
「彩美はどう思うだろう。あのコは、私の服装の真価を正しく評価できるだろうか。もしかして、彼女は、この店のトロフィーワイフたちが身に着けている、日曜日の午後の番組のスタジオで見かけるみたいなきらびやかなファッションに圧倒されてしまうかもしれない。そして、自分の母親の、いかにも風采の上がらない立ち姿と、容姿の衰えと髪の色の輝きの無さに、ショックを受けるかもしれない。そう思うと、彼女は、この店に座っていること自体に、次第に強い圧迫を感じはじめる。どうしよう。あと20分もすればあのコがやって来る。あのコは、あのエントランスのあのドアから、この店のこの席に座っている私を見つけて、立ち止まることだろう。午後の日差しを顔の前面いっぱいに浴びて、小じわの目立つ寝不足の肌と、生え際に伸び始めてきている白髪が浮き上がって見える私の姿を5年ぶりに直視して、あのコは、走り出して逃げてしまわないだろうか」
静子は、立ち上がっている。そして、まだ口をつけていない紅茶に一瞥を与えることもせず、彼女は、伝票を取り上げると小走りにレジに向かう。
「急いで」
1000円札をギャルソンに渡し、釣りを受け取ると、彼女は、店を出て、そのまま駅とは反対方向に歩きはじめる。しばらくすると、彼女は、ほとんど全速力で等々力方面に走りはじめている。
彩美には、いずれ機会を見て話をしないといけない。自分がどうして腹を痛めた娘を折り合いの良くない実家の母親に押し付けて、東京で暮らしているのかについて、13歳の娘にきちんとわかるように筋道立てて説明せねばならないだろう。
でも、その時にどんな言葉で説明するのであれ、今はその時ではない。私は、まだ準備ができていない。私はまだ自分が失敗した母親である事態に直面できていない。それどころか、私は自分が失踪した男の内縁の妻であった事実から自由になっていないし、自分が誰かのトラップであり、誰のトロフィーでもなく、もしかしたら自分自身であるのかどうかさえあやふやであることを、きちんと自分に説明できていない。
2時間後、東急大井町線の上野毛駅から静子は溝の口方面の電車に乗った。どこに行くあてがあるわけではない。また引っ越しをしなければならないとなんとなく思っている。
その前にスマホを解約せねばならない。
小田嶋隆(おだじま・たかし)
1956年、東京赤羽生まれ。早稲田大学卒業後、食品メーカーに入社。営業マンを経てテクニカルライターに。コラムニストとして30年、今でも多数の媒体に寄稿している。近著に『小田嶋隆のコラム道』(ミシマ社)、『もっと地雷を踏む勇気~わが炎上の日々』(技術評論社)など。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事






