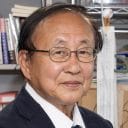きれいなものは探さないと見つからない――いまテレビドラマは何を描くのか?『いつ恋』最終話
#テレビ #ドラマ #高良健吾 #有村架純 #スナオなドラマ考 #いつ恋
 フジテレビ『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』
フジテレビ『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』
ドラマ『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』の最終話となる第10話が放送された。全10話を通して、テレビドラマというジャンルと正しく向き合い、美しい物語を、ただただ誠実に描いたこの作品は、いまこの時代にテレビドラマは何を描くかという問いにも真っすぐに向き合っていた。それはつまり、生きている人を描くということだ。
すでにテレビは、誰もが見るものではない。放送時間になったらテレビの前に座って、CMも飛ばさずに1時間近く体を拘束されるという視聴形態は、いかにも古い。テレビを見ている人は、もはや多数派ではなく少数派だ。毎週毎週、リアルタイムでテレビドラマを見るという層はいまこの時代にはマイノリティであり、新しい娯楽メディアに乗ることのできない寂しい人だ。だからこの作品は、生きている人を描く。視聴者の寂しさをまぶしい時間で紛らわせるのではなく、生きている人を描くことによって、視聴者の胸に花の種を植える。その花は、いま咲き誇って寂しさを忘れさせることはできないが、いつか咲くものとして私たちに与えられる。
前回、引ったくりに遭った少女(芳根京子)と出会った音(有村架純)は、何も知らずに勝手な善意を振りかざす人々と引ったくり犯のもみ合いに巻き込まれ、転倒して意識を失う。病院にやって来た少女は、引ったくり犯は悪くないと説明しようとするが、朝陽(西島隆弘)は「人をケガさせて悪くないわけないよね」「引ったくりは引ったくりだろ」と、耳を貸さない。少女は音の身を思い、「ほっといてくれたらよかったのに」とつぶやくが、それを聞いた練(高良健吾)は彼女に告げる。
「杉原さん(=音)は、放っておいたりしない。通り過ぎたりしない」
それは杉原音という人間のパーソナリティを的確に表現しているが、同時にこの作品の本質でもある。誰のことも放っておいたりせず、通り過ぎることはなく、すべての登場人物が生きる姿を描く。物語を進めるためだけに配置されたキャラクターは、少なくとも主要な登場人物の中にはひとりもいない。
たとえば最終話、朝陽と音との別れの場面もそうだ。朝陽は、音の亡き母親が音に宛てた手紙を読み、自ら別れを切り出す。「お見合いしろって言われてるんだよね」と、見え透いたウソまでついて。「僕はもう、君のこと好きじゃない」と繰り返す朝陽の姿は、その言葉がウソであることが分かるからこそ愛おしく切ない。だが音のアパートを出た朝陽がすがすがしい顔で空を見上げる様子は、彼の人生が今また始まったことを私たちに告げている。朝陽は音という大切な人と別れることにはなったが、彼女との出会いは種として彼の胸に植えられたのだし、これからの生き方の指針になり続けるだろう。音との思い出は、朝陽にとってもまた「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」ものだ。
晴太(坂口健太郎)は小夏(森川葵)から「私にはウソつかなくていいよ。っていうか、私は晴太のウソも本当も全部まとめて信じてあげる」とその人生をまるごと認められ、泣いている顔を着ぐるみで隠しながらも「初めて会ったときから大好きです」と、本当の気持ちを飾り気のない言葉で告白する。木穂子(高畑充希)は自分の仕事と正しく向き合い、一歩先へ進もうとしている。朝陽の兄は、妻の実家の旅館で働くことにしたと前向きな表情を浮かべて語り、かつて妻子から愛想を付かされた佐引という練の職場の先輩は、ハートマークの手作り弁当を同僚から冷やかされている。これらすべては、わかりやすくドラマチックなものではない。奇跡という言葉で語られるようなものではなく、少し探せばどこにでも誰にでもあるような話だ。だが音は、亡き母へ宛てた手紙で言う。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事