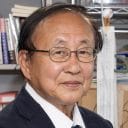東国原英夫の「失言」が示す、2014年以降のテレビのあり方『ワイドナショー』(12月21日放送)を徹底検証!
#松本人志 #東国原英夫 #タレント解体新書
 『ワイドナショー』フジテレビ
『ワイドナショー』フジテレビ2014年もまたさまざまな出来事が起こった年ではあったが、テレビでは果たして何が起こっていたのか。今年のテレビを象徴する人物として名前が挙げられるべきは、芸人でも、俳優でも、アイドルでもないだろう。佐村河内守氏と新垣隆氏であり、小保方靖子氏であり、野々村竜太郎氏であるはずだ。少なくとも2014年のテレビを席巻し、視聴者の欲望を満足させたのは、ドラマやバラエティではなく、彼らのリアルな記者会見の姿であったことは間違いない。
テレビは時代を象徴するものだから、テレビを考えるということはその時代を考えることでもある。では、2014年はどういう時代なのか? 一言で言ってしまうと、「むき出しの時代」ということになるかもしれない。キャラクターの強い人々の記者会見を楽しむという行為は、下世話を通り越してむしろ下衆とも言えるが、その善悪はともかくそれが今のモードである。かつては品がないとしてどこか遠慮があったものだが、その考え方は古い。何しろ「むき出しの時代」なのだから仕方がない。
それは、世間で起きたさまざまな事件にも感じ取ることができる。ヘイトスピーチであれ、安倍首相の発言や政治行動であれ、あるいは先日のJR東京駅で起きた記念Suicaの発売におけるゴタゴタも、まさしくその一例だろう。「すべての人に行き渡るように販売する」と言う駅員に対して「それだと転売できねえんだよ!」と声を荒げるというのは、まさしく2014年的だ。身も蓋もない。恥という意識がそこにはない。誰もかれもがむき出しである。ここ数年は「可視化の時代」と言われていたわけだが、それがエスカレートして「むき出しの時代」に突入したのが、2014年だと言えるだろう。
そしてテレビはまた、その時代の変化を感じ取りながら、世間に対してその時代なりのアプローチをする。その最も象徴的な番組が、松本人志がコメンテーターとなり、世の中のニュースについて語る『ワイドナショー』だ。2014年4月からは、それまで『いいとも増刊号』を放送していた枠に移動、というのもまた象徴的である。そもそも松本人志は、世間の変化に対して非常に敏感であり、独特の嗅覚を持っている。というか、売れる芸人にはそれが必ずあるわけだが、『ワイドナショー』もまた彼の嗅覚の鋭さを示している。確かに時代は変化しているのだ。
だが、その時代の変化を感じ取れずに、うまく対応できていないタレントも、また存在する。12月21日に放送された『ワイドナショー』のゲストは、長嶋一茂、ホラン千秋、そして東国原英夫であった。取り上げたニュースは、小保方氏のSTAP細胞問題に終止符が打たれた、というもの。長嶋一茂は「STAP細胞が見つかったと聞いて、希望を持った人がいるのに」と語り、ホラン千秋は「小保方氏を心配してしまう」と、女性目線からの意見を投げかけた。
そして、その後に続く東国原英夫のコメントは、次のようなものだった。
「待ってるドナーがいるわけですよ。僕、どれぐらい期待したか」
そう語った瞬間、完全に微妙な空気がスタジオに流れる。要は、自身のハゲネタに持っていこうとしているのだ。しかし明らかに、東国原英夫に求められているコメントはそっちではない。松本人志が「もうね、すぐそうやってハゲネタに逃げるでしょ?」と返して一応の流れは断ち切られるのだが、これは明らかに東国原英夫の作戦ミスだと言うしかない。
政治家としての手腕はともかく、タレントとしての東国原英夫は優秀である。少なくとも、これまでは優秀であった。その優秀さは、空気を読むうまさ、という点に尽きる。たけし軍団で鍛えたその能力は、特筆すべきものがある。だがしかし、残念ながら、ずれてきてしまっている。時代が、あるいは『ワイドナショー』が求めるものを、勘違いしている。これは、かなり致命的なものだ。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事