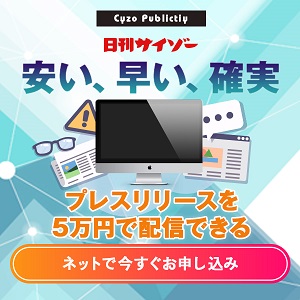「僕が今もし20歳だったら、けっこう燃えていた」佐久間正英が見通す、音楽業界の構造変化
#リアルサウンド
【リアルサウンドより】
日本を代表する音楽プロデューサー佐久間正英氏が、音楽シーンへの提言を行う集中連載。ライブハウスをはじめとする音楽界の問題点を指摘して大きな反響を呼んだ前編「『今はライブ全盛』は一面的な見方 ライブハウスのシステムに無理がきている」につづき、中編では音楽業界の収益構造の変化と、ミュージシャンがその中でどう活動すべきかを語った。
――第一回では、音楽界を取り巻く現状と問題点について伺いました。佐久間さんはそれを冷静に分析した上で、悲観することなく新しいことをすればいい、というお考えですね。
佐久間:そうですね。保守的な立場の人は「これまでのような仕事ができない」「お金も入ってこない」と悲観するかもしれませんが、僕はただのミュージシャンだから。俯瞰してみると、これまでの業界の構造が劇的に変化している面白い時代だし、僕がもし20歳だったら、けっこう燃えていたと思いますよ(笑)。
――昨年、佐久間さんがブログに書かれた「音楽家が音楽を諦める時」という記事は、大きな議論を呼びました。こちらも、予算の制約が厳しく、これまでのような制作は難しくなっているという現状を明らかにする内容でした。
佐久間:別に責任感を持って業界の問題を訴えようと考えたのではなく、ただ現実を書いただけですが、「音楽を作るのにお金が必要だということを、みんな忘れていないか?」という思いはあります。楽器を買うにもスタジオに入るにも、ライブハウスに出るにもお金がいる。移動するためには車を持たなきゃいけない。若いバンドでいうと、練習に時間をかければバイト代は減るので、これもコストと言えるかもしれない。これがレコーディングとなれば、リアルにより多くのお金がかかるんです。
――現実に、かなり名の通ったミュージシャンでも「生活するのが厳しい」というケースがあると聞きます。
佐久間:ミュージシャンがお金を稼ぐための方法も変化していて、それはCDでもなければ、あるいはライブそのものでもなく、ライブ会場でのグッズの売り上げだったり、ファンクラブの会費だったりする。アメリカのバンドとは違い、日本のバンドはライブのギャラだけでは生活できません。ライブハウスのシステムの問題もあるし、「お金を払ってライブに行こう」という音楽人口の絶対数が少ない、ということもあります。
<!– Separator for PageBute –>
――グッズやファンクラブから収入を得るというのは、必ずしも作品そのものではなく、送り手側のライフスタイル全体をビジネスとするような感覚ですね。
佐久間:エンターテインメント産業としてはそれで間違っていないし、例えばAKB48のようなやり方も正しいと思います。ただ、音楽という考え方をした場合に、ライブで食べることができず、またCDが”グッズ”のひとつになってしまっていることは残念に思います。売れているバンドのグッズ売り場は長蛇の列。そのなかで一番売れないグッズがCDという状況なんです。
この時代に、レコード会社がどんどん潰れていくのは仕方ないと思います。気の毒ではあるけれど、商売として新しい環境に適応できなかったツケが回ってきただけ。でも、これから音楽を志す人たちにとって、夢がなくなってしまったことが苦しいですね。生活できないからという理由で音楽を趣味にとどめたり、夢を捨てきれずフリーターをしながらライブを続ける……という状況は、やっぱり寂しい。
――見方を変えると、音楽産業が高い利益率を誇った50年くらいが、ポピュラー音楽の歴史の中で特別な時代だった、ということでしょうか?
佐久間:そんなことはないと思いますよ。全世界的に見てこれから音楽産業が衰退していくかというと、僕はそうは思わない。例えば最近、台湾の人気アーティスト・AARON(アーロン)くんのアルバムを聴いたら、クオリティが本当に高い。日本ではこんなにきちんとしたレコーディングはできない、というレベルです。台湾でCDが売れているかというとそんなことはないし、別のビジネススタイルが確立しているはず。日本の音楽業界は、新しい環境への対応が下手だったな、と思います。いろいろと話しを聞くと、今はアジアでも日本は相手にされない、というのが現実のようです。シンガポールで「日本の人とは仕事をしません」と露骨に言われた、という音楽関係者の話も聞いたことがある。幸いロック・バンドに関してはこれに当てはまりませんが、いわゆるポップスについてはクオリティが低いと思われている。韓国のポップス業界でも、プロデューサーはアメリカから呼びます。日本から呼べば安上がりなのに、と思いますが、音楽としての質を保てないと見抜いているのでしょう。
――制作体制も含め、日本の音楽の質が低下しているのだとしたら、そうした問題意識は多くの人に共有されているでしょうか。
佐久間:日本で音楽をやっている若い人の多くが、そうは思っていない。リスナーもいい音を知らずに育ってしまったから、クオリティが低いことに気づくことができないんです。かつては、僕が録ったものの質が低ければレコード会社に怒られたものですが、今は制作にかかわっている人たちが、音の良し悪しを聴き分けることができない。極端な話、生のピアノ、生のドラムで録音したことがないレコーディングエンジニアも出てきています。「カッコイイか」「キッチュか」という感覚的な判断しかできないのです。
アメリカではどうか。レコーディングのやり方も、音に対する捉え方も、基本的には昔と変わっていません。売れている作品を聴くと、HIPHOPはまた別ですが、素晴らしく音がいいものが多い。音楽のクオリティの低下は、やはりテクノロジーや環境だけのせいにはできない、ということです。
(取材・文=神谷弘一)
後編に続く
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事