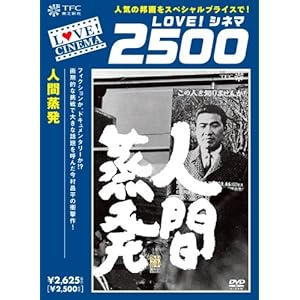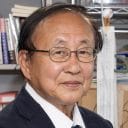被災地の実態から山口組組長直撃取材まで ──タブーなき名作ドキュメンタリーの世界
#闇社会 #ドキュメンタリー
──需要が少なく陽の目を浴びることがなかったテレビのドキュメンタリー。テレビ放送黎明期から製作されてきたこれらの作品は、今日のテレビ番組制作に大きな影響を与えているという。その歴史や影響、現在のシーンをたどりつつ、隠れたテレビドキュメンタリーの名作を紹介していく。
このところ、テレビドキュメンタリーに注目が集まっている。もちろんこれまでも話題となる番組はあったが、ドラマなどに比べると再放送も、DVD 化されることも極めて稀だった。それが、戸塚ヨットスクール事件のその後を扱った東海テレビ制作のテレビ番組『平成ジレンマ』(10年5月放送)や、四日市公害の闘争を扱った、やはり同局制作の『青空どろぼう』(10年11月に放送された『記録人 澤井余志郎~四日市公害の半世紀~』を劇場用に再構成した作品)などが劇場公開されたり、また、山形国際ドキュメンタリー映画祭でも60年代から70年代の秀作を中心にテレビドキュメンタリーの特集上映が組まれ、その魅力が再発見されている。
長年、ドキュメンタリー映画に関する隠れた良作を発掘し、神保町のneoneo坐などで上映活動を行っている清水浩之氏は、テレビドキュメンタリーへの関心がにわかに盛り上がり始めた背景についてこう話す。
「これまでドキュメンタリー作品では、テレビ番組はほとんどまとめられていなかった。それを岩波書店が2年前、『シリーズ・日本のドキュメンタリー』というDVD付全集を編む時に、初めて資料にまとめようという動きが出てきたんです。この資料の中に、放送業界内では有名な作り手が制作したものや、評価の高い作品が結構あるんですよ。だけど昔のものに限らず、リアルタイムでも一般人が簡単に見られる作品はほとんどない。例えば、地方局である東海テレビ制作のドキュメンタリーは、かならずしも系列キー局のフジテレビで放送されるわけではない。なので、もっと見せる機会を増やせないかということで、東海テレビの阿武野(勝彦)さんの発案で、『青空どろぼう』を劇場公開する流れになったんです」
このように劇場公開できるほどの良質な作品は、とくに地方局から生まれやすいという。
「地方局にとって、地元の状況や事件を扱ったドキュメンタリーは、キー局に比べて地方局ならではの”強み”が発揮できるジャンルなんです。地元取材なら、東京から取材に来たスタッフとも互角以上に渡り合える。また、視聴率よりも、賞狙いで番組を作っているようなケースもあります。60年代から福岡の RKB毎日放送にいた木村栄文という伝説的なディレクターは芸術祭賞などを多数受賞して、『賞獲り男』って言われていたくらいですから。賞を獲ることで評価されて、また次の番組を作ることができる、という構図もあると思います」(清水氏)
ドキュメンタリー作家である松江哲明氏も、やはり地方局で生まれる作品に注目しているという。
「地方局は、あるテーマに取り組むときに、ひとりのディレクターだけでかかわることが少ない。地域との関係性の中で、先輩ディレクターから引き継いだり、同僚と連携しながら、集団で取り組んでいく。そうやって、長年被写体に密着しながら番組を作っていく体制は、映画のドキュメンタリーではなかなかできるものじゃないですね」(松江氏)
松江氏が衝撃を受けたという『青空どろぼう』も、長期に渡る丁寧な取材があった。
「ドキュメンタリーが特に力を発揮するのは、声を持たない人たちや、はっきりとは映らない空気のようなものを掬いとる時だと思うんです。『青空どろぼう』も、企業が国ぐるみで大きなモノを優先させるときに、その影で犠牲になる人たちの小さな声を緻密に取り上げている。僕にとっては、今年観たドキュメンタリーで、ベストのうちのひとつだといえる素晴らしい作品でした」(松江氏)
■ドキュメンタリーの旗手田原総一朗の偉業とは?
さて、良作のテレビドキュメンタリーが映画化されたり、ソフト化される動きに加え、オンデマンド配信や動画共有サイトなど、テクノロジーの発達もこの盛り上がりに一役買っているのではと、清水氏は語る。
「84年から89年に掛けて起こった山一抗争の頃に、NHKが山口組を取材したドキュメンタリー『山口組 知られざる組織の内幕』(84年8月放送)という作品があるのですが、これは4代目竹中正久組長を始め、若頭などが勢ぞろいで出演。さらに対抗組織だった一和会の組事務所の中にまでカメラが入っている。間違いなくNHKは再放送もオンデマンド配信もしないでしょう。ところがこの作品を誰かが録画して持っていて、動画共有サイトに不定期にアップされる(笑)。もちろん発見されると削除要請されて消えてしまうのですが、また上げられるというイタチごっこが繰り返されています」
こうしてこれまでは気軽に見られなかった隠れた名作に、手が届きやすくなった。この機運に乗じて盛り上げていくには、「埋もれてしまった名作を紹介する”キュレーター”的な役割が重要であり、そうした需要も高まってきているのでは?」と、清水氏は語る。
そんな中、10月に開催された山形国際ドキュメンタリー映画祭では、60年代から70年代のテレビドキュメンタリーの特集が組まれた。
「私も作品の選定にかかわったのですが、ドキュメンタリー映画って監督の名前だけで売れるようなところがありますが、テレビ番組の場合、その性質上、どうしても作り手がテーマの影に隠れがちなんです。
この頃活躍した人だと、例えば、NHKには工藤敏樹という緻密なドキュメンタリーを作るディレクターがいた。日テレには牛山純一という民放のドキュメンタリーを一から創った名物プロデューサーが、TBSには、後にテレビマンユニオン(映画監督の是枝裕和が所属するドキュメンタリーに強いテレビ制作会社)を設立する、萩元晴彦や村木良彦という実験性に富んだドキュメンタリーでテレビ的表現を拡張したディレクターがいた。彼らの作品を切り口にしたら、とアドバイスしたんです。
この時代は、テレビがまだニューメディアだった。番組の作り方も確立しておらず、いろいろな試行錯誤がされていたんです。最初は映画のやり方をマネしてみたり、ラジオの構成を取り入れてみたりしている。今見ると、かなり変だけど、面白い番組がいっぱいあります」(清水氏)
また、前記の作り手たちに並んで、清水氏が、テレビの表現を開拓した重要な人物として挙げるのが、現在もジャーナリストやキャスターとして活躍する田原総一朗である。
「田原さんもやはり同じ頃にテレビ東京に入って、ドキュメンタリー番組を作っていました。当時のテレ東はNHKやほかの民放局に比べて、今以上に予算もないし、視聴者も少ない。そんな環境で、田原さんは、かなり過激な番組作りで、テレビドキュメンタリーの表現を探っていった。例えば、ジャズピアニストの山下洋輔が出演した『バリケードの中のジャズ~ゲバ学生対猛烈ピアニスト』という番組は、学生運動吹き荒れる早稲田大学のバリケードの中に山下洋輔をピアノと一緒に放り込んで、ピアノを弾きまくらせるというむちゃくちゃな企画。きっかけは山下洋輔がどこかで『ピアノを弾きながら死にたい』と言ったのを聞いた田原さんが『面白い、俺が殺してやる』って、死に場所としてバリケードの中をチョイスしたそうなんです。その思いつきを実行してしまう豪腕ぶりが抜群に面白い」(清水氏)
また松江氏は、現在も放送されている『朝まで生テレビ!』(テレビ朝日)を例に挙げつつ、田原の制作手法について語る。
「田原さんの場合、ドキュメンタリーの制作において、結論を出さないままで放り投げて、まとめ上げることなく番組を終わりにしてしまう。テレビなら放送時間が決まっているので、どんなに放り投げても、番組の放送時間終了とともに、ちゃんと終わりがくるんですよ(笑)。こうしたスタイルは『朝生』にしっかり継承されています。田原さんはよくあの番組について『結論なんかでなくていい』と言う。でも、どんなにケンカになろうが、議論がしっちゃかめっちゃかになろうが、朝がきたらスパッと終わる。田原さんの番組を見ていると、(ひとつの作品としてお金を取って上映する)映画のドキュメンタリーとは違う、テレビドキュメンタリーならではの可能性があると思います」(松江氏)
■ドキュメンタリーの現代的な楽しみ方とは
このようにテレビの”青春期”にドキュメンタリーの作り手たちが生み出した手法には、その後の番組作りに多大な影響を及ぼしたという。
「66年にTBSの萩元さんたちが作った『あなたは…』という番組では、道行く老若男女に無差別に同じ質問をするんです。その質問を寺山修司が考えているのがまた面白いんですが、例えば『日本人は悲劇ですか? 喜劇ですか?』や『(アメリカ人に向かって)原爆に責任を感じてますか?』など、独特な質問をぶつけて、そのリアクションを見る。それまではタレントやキャスターが何かを発信するというのがテレビ番組の基本でしたが、この頃『リアクション』が発見されたことで、素人も番組で”いじれる”ようになった。これはバラエティ番組の原点とも言えるでしょう」(清水氏)
確かにこうした手法は今日のテレビ番組では当たり前のもの。それと同時に、時代とともにそれらはアップデートもされている。自らも作り手である松江氏は語る。
「例えば、『痛快!ビッグダディ』(テレビ朝日)みたいな大家族モノって、出てる人たちが自分の役割をよくわかってるところにある。彼らは素人ですが、頭のどこかにかつてテレビで見た大家族モノのフォーマットがインプットされていて、それに合わせて、自分がどう動くべきかをどこかで理解しているように見えます。例えば『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ)でも『漂流家族』という、大家族ものがあるんですが、その中で旦那が妻を殴ろうとするんですけど、そのカメラアングルが絶妙なんですよ。旦那が手を振り上げた瞬間に、妻がカメラの手前にいる子供たちに向かって、大声で『出ていくよ!』って言うんです。いくらなんでも芝居がかりすぎだろっていう(笑)」(松江氏)
かつて今村昌平が映画『人間蒸発』(1967年)の中で、撮影の一環として女優のプライベートを隠し撮りして、「やりすぎだ」と議論を呼んだことがある。その際、今村は「カメラで隠し撮りでもしないと人間の本音は炙り出せない」と言ったという。しかし、松江氏によれば、むしろ今のテレビドキュメンタリーの核心は、カメラを向けることで演じ始めてしまう被写体から、漏れる本音を拾うところにあるという。
「今村さんの時代とは隔世の感がありますよね。半年ぐらい前に放送された『ザ・ノンフィクション』で女性アイドルの生き方に迫った『アイドルすかんぴん』では、番組放送後、出演者が撮られ方への不満を告白して話題になりました。自分のプライバシーを曝かれたというクレームではなく、自分がイメージしていた映り方と、番組サイドの編集に誤差があって、それが許せない、ということでした。でも、ドキュメンタリーを制作していく上で、そのズレはどうしても生じるもの。すごいディレクターだと、そのズレをあえて意識して制作しているフシがみられる。カメラを向けまくることで、ぽろっと漏れてくる本音、それを見るのが、今のドキュメンタリーの楽しみ方のひとつですね」(松江氏)
今旧作や地方局を中心に、光が当てられているのは、テレビという表現が持つ意味を、制作体制や視聴方法も含めて、もう一度、考えてみようという機運なのではないか。
(文=九龍ジョー/「プレミアサイゾー」より)
■プレミアサイゾーとは?
雑誌「サイゾー」のほぼ全記事が、月額525円で読み放題!
(バックナンバー含む)

つくりものと真実に境界はあるのか
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事