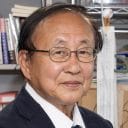地元紙は”アルジャジーラ”になれるのか?『河北新報のいちばん長い日』
#本 #東日本大震災
仙台市を拠点にニュースを発信し、宮城県内で48万部の発行部数を誇る地方新聞・河北新報。宮城県の世帯数が91万世帯というから、単純に計算すれば県民の半数以上が閲読している計算になる。そんな河北新報社から、震災後の同社の動きを記録したルポルタージュ『河北新報のいちばん長い日 震災下の地元紙』(文藝春秋刊)が発売された。
前例のない震災を経験して戸惑う現場。ガソリンが尽きそうになる中、続けられる取材活動。がれきの中の配達。新聞制作現場からのルポは、あらためて震災の大きさ、恐ろしさを浮かび上がらせる。また、記者として前線に出ることのできない辛さや、前線にあっても被災者を助けられず取材をすることしかできない苦しみ、避難したものの、報道人としてそれが適切であったのかについて悩まされる描写に現れる葛藤は、一介の地方新聞社という枠を越え読者の心を打つ。
震災が起こった当初、「われわれはみな被災者だ」と河北新報報道部次長の鹿又氏は言った。
河北新報では、津波によって支局が流され、販売拠点も多く失った。販売員やその家族たちも犠牲になった。しかし、河北新報が「被災者」と考えるのは、それ以上に「地元」が傷つけられたという悲しみによるものだ。
首都圏に軸を置く全国紙とは、「地元」へのこだわりが決定的に異なる。例えば、震災直後の死者数を伝える見出し。「死者1万人」なのか、「犠牲1万人」なのか、伝える事実は同じであるものの、その言葉が与える印象は大きく異なる。他紙がよりインパクトのある「死者」という言葉を選ぶ中、河北新報は「犠牲」という言葉を選んだ。被災者は「死者」という言葉を受け取ることができないのではないか、という判断だった。
新しいメディアに対して、新聞は「遅れた」メディアであるとされることが多い。ネット上で即時に伝えられる情報とは違い、新聞は毎朝・夕の2回しか発行されず、アーカイブもしにくい。しかし、今回の震災では、その「遅れている」ことが功を奏した。
停電によりテレビもつけられない。携帯電話も不通。急いで避難してきたからラジオを持っている人もごく一部。そのような状況となったときに、新聞の力は発揮された。これまで培ってきた強力な販売網によって避難所に運ばれた新聞の山はあっという間になくなってしまった。人々はそれを手にすると、むさぼるように読んでいた。外がどのような状況になっているのかも分からない。どれくらいの津波が襲ったのかも定かではない。生活インフラの復旧はいつになるのか。いつもは空気のような存在だった新聞のもたらす情報は、被災者にとっては単なる知識以上に死活問題だったのだ。
この20年間にさまざまなメディアが出現したことによって、新聞、特に地方紙の役割もだんだんと変わりつつある。20年前であれば河北新報は宮城県民や一部東北の住民だけを念頭に紙面を制作していればよかった。しかし、インターネットによって配信される記事は、県境を越え、世界中からのアクセスを可能にする。地元の声をそのまま日本中に広めることも可能になった。
ジャーナリストの津田大介氏は自身のメールマガジンで「地方新聞をはじめとするローカルメディアに求められているのは、『どうやって日本のアルジャジーラになるか』という視点ではないか」と語る。震災から月日が経てば、大手メディアはほかのニュースを追い求めて規模を縮小したり、引き上げてしまうことも多い。しかし、仙台に本社を置く河北新報には当然引き上げる場所はない。「あそこ」で起こった震災ではなく、「ここ」で起こった震災として、今でも被災者に寄り添った報道を続けている。それは、全国をカバーする大手メディアにも、組織を持たない個人が発信するTwitterやブログにも真似できない「報道」のあり方なのではないか。
本当に、新聞は「遅れた」メディアなのだろうか?
(文=萩原雄太[かもめマシーン])
報道とは何か。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事