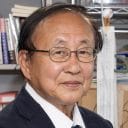「テレビは権威ではない」ものづくりを手放したキー局とローカル局の未来
#テレビ #テレビマンに訊く
地デジ化による膨大な設備投資・広告収入の減退・ネットメディアの台頭など、かつてない窮状を抱えていると言われるローカル局。地方から全国区への人気を博した『水曜どうでしょう』(北海道テレビ/以下、『どうでしょう』)のような番組は、キセキか、それともローカル局の知られざる潜在能力なのか。
『どうでしょう』の立役者であり、このほど『けもの道』(メディアファクトリー)を上梓したディレクターの藤村忠寿氏に、ローカル局の今と、来たるべき未来の姿を聞いた。
――3月から4年ぶりの新シリーズがスタートしましたね。ローカル局のいちコンテンツだった『水曜どうでしょう』は、もはやキー局もがモデルにするお化け番組になっています。新シリーズを始めるに当たってのプレッシャーはありましたか?
藤村氏(以下、藤村) よく聞かれるんですが、特にプレッシャーはなかったです。われわれは何も変わってないですから。逆に無理する方が難しい。会社はもちろん利益を求めますけど、スタッフは相変わらず二人だし、僕たち自体のスタンスは何も変わらない。見てくれる人たちが増えたというだけなんです。
――『どうでしょう』以降、東京でも似たような番組が増えたことは確かです。
藤村 どこかに行って、スタッフがタレントに無茶を言って……っていうやり方をマネるだけならできると思います。でも、それだけでは『どうでしょう』にはならない。あの番組は、大泉洋と鈴井貴之とディレクター嬉野と僕っていう4人の人間関係で成り立っているから。このバランスが一つでも崩れたら別の番組になっていたと思いますよ。

――『どうでしょう』の「楽しそうなことやってる」ところだけを切り取っても、視聴者からの共感は得にくいですよね。視聴者を置いてきぼりにし、いわゆる”業界内視聴率”信仰のみが暴走するというか。藤村さんが上梓された『けもの道』に「番組は(一般)視聴率ありき」と書かれていましたが、非常に合点がいきました。
藤村 僕は「楽しいことがやりたい」っていうヤツを信頼しないようにしているんです(笑)。あの番組は決して楽しんでやっているわけじゃない。楽しめる状況を作っているだけです。そもそも視聴率が取れなければ、テレビ局で番組を作る意味がない。ロケ中は番組を面白くすることだけを四六時中考えてます。それは大泉くんにしても鈴井さんにしてもそう。現場の人間が面白さ・キツさ・怒りも含めて「本気」じゃなければ、見ている人に伝わらない。だから「楽しそうだよね」と言われることには違和感があるんですよ。
ただ、今は視聴率がすべてだとは思っていません。DVDやグッズの売り上げでコンテンツの価値は変わりますから。『どうでしょう』は1999年に北海道で20%近い視聴率を記録したけど、それ以降、数字は上がっていない。今シリーズも平均で13%です。じゃあ、今より99年の方が面白かったかというとそうじゃない。数字だけを追っていると本質を見失うことがあるのも事実です。要するに、大事なのは視聴者が本当に面白いと思ったのかどうか。ローカル局は視聴者の顔が見えるから強いんですよ。数字が少し上下したくらいであたふたしない。だって僕たちが迷い始めたら、番組は変わってきちゃうでしょ。やっぱり「『どうでしょう』は相変わらずだね」と言われないと。
――地デジ化をはじめとして、テレビ局、特にローカル局を取り巻く環境がますます厳しくなると言われる中で、『どうでしょう』が理想的なビジネスモデルとして存在しているのは、まさにそういう部分なんですね。
藤村 偉そうなことを言えば、テレビは文化なんです。ほとんどの人が長年にわたって見ているものですよね。でも、権威ではない。作り手と見る人の身分になんら違いはないんです。しかし、現在のような東京一極集中では文化とは言えない。多様性こそが文化ですから。”北海道に住んでる人間が北海道のペースで作る番組”というのを大切にしなければ。それは東京ではできないことですし、それこそがローカル局の役割だと思います。
しかし、ローカル局の人は東京で作ってるものを目指してしまいがちなんですよ。規模も予算も人も環境も違うんだから、一生かかっても同じものはできないんです。それなのに、ローカル局の人間が東京にドラマや報道の研修に行ってどうすんの? って話ですよね。そんなことをしていたら、どの局を見ても一緒になってローカル局の立ち位置はますます揺らいじゃいますよ。
――まさに今回の著書のテーマでもある「自分の役割を見つける」というところに通じるお話ですね。藤村さん自身は北海道テレビにいて、ローカル局、またテレビ全体の「危機」みたいなものを感じますか?
藤村 僕ね、ローカル局はキツイとは別に思っていないんですよ。テレビは電波塔を持ってて、免許事業だからそう簡単にはつぶれない。じゃあなんで「キツイ」って声が聞こえてくるのかといえば、キー局も含めてテレビ局が「作る」という部門を手放しちゃったから。これからはメディアの強さではなく、コンテンツが面白いかどうかで決まってくる。画像を使ったエンタテインメントを作ることに関して、歴史的に考えてもテレビは最強だったんです。それを制作プロダクションに切り離してしまったことが、テレビ局が焦っている一番の要因なんじゃないですかね。自分たちで作っていたら、ネット・DVD・その他メディアへの露出の転換もフレキシブルですからね。広告収入の減収とか言いますけど、いいものを作れば絶対に広告宣伝費は付いてきます。見てくれている人が喜んでくれるものを一生懸命作る。局が「うちにはコレがあります!」っていうスタンスでいれば何も怖くないと思いますよ。
――そういった、ひたすら防御する方向に向かっているテレビ局へのいら立ちはありますか? テレビだけでなく、広い意味での「見せる側」が過剰な規制をかけている現実があると思うのですが。
藤村 僕らの世代(40代)は、テレビが一番無茶していた番組を見ていた時代でもあります。だからこそ、今の抑えつけられた状況を「おいおいいいのか?」って思いますよ。それは僕だけでなく、業界にかかわる人間は誰しも思っているんじゃないですかね。都心のど真ん中に立派な社屋作ったら、もう無茶できなくなっちゃうでしょ。あれは”権威”の象徴ですからね。でも、東京を変えるのは難しいと思います。だからこそ、コンプライアンスが絶対で、些細なことにも承認を得なければならないという窮屈な空気を、地方から少しずつ破っていかなきゃいけないと思いますね。法を犯すのではなく、表現の幅を取り戻すというか。それもローカル局のひとつの役割ですよね。
――「テレビがモザイクだらけになる」という笑えない冗談が現実になってしまいますよね。
藤村 だからこそ、僕らの世代がいったん捨て石にならなきゃいけないんですよ。それこそ「テレビが全部モザイク」になる前に、「ちょっと待った!」と声を上げる。「いいじゃん、これくらいは別に」って。それをやると、「何を言っているんだ!」ってバッサリ切られるんです、たぶんね。でも一人がバッサリ切られ、次もまたバッサリ切られっていうのを繰り返して、それで社会が少しずつ動いていけばいいんじゃないかなって。それができるのは、超マジメな20代でも、慎重過ぎる30代でも、危機感すら感じていない50代60代でもなく、特に苦労せず今まで生きてきて、出世にもガツガツしてない僕ら気楽な40代だと思うんですよ。
――頼もしい! 藤村さんはこれからも現場に出続けるおつもりですか?
藤村 そこが僕の一番楽なところですから。僕と同い年で編集機をいじってるの、北海道テレビではたぶんほかにはいないんじゃないかな。偉くなるとみんなパソコンの前で要らないメール出し始めるでしょ。「つなげよ、画を」と思いますね。僕たちにはそれしかないんだから。50になっても60になってもやっていくつもりですよ。
(取材・文=西澤千央/写真=後藤匡人)
●ふじむら・ただひさ
通称、藤やん。1965年生まれ、愛知県出身。90年に北海道テレビ(HTB)に入社。東京支社で編成業務部に配属。95年に本社の制作部に異動し、ディレクターに。96年にチーフディレクターとして『水曜どうでしょう』を立ち上げる。番組には、ナレーターとしても登場。テレビドラマや舞台の演出、他局のテレビ出演や講演会、プロモーションビデオの制作、アニメの声優、新聞や雑誌での連載、対談本発売など、マルチに活躍中。
ズル賢く。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事